コントラストの原理とは、二つ以上の異なる刺激を比較し、その違いを通じて各刺激を理解するという人間の傾向のことです。
私たちは日々、無数の選択を迫られます。何を食べるか、何を買うか、どの情報を信じるか。しかし、これらの選択は本当に自由な意志から生まれるものなのでしょうか。
実は、私たちの選択は「コントラストの原理」という心理学的なメカニズムに大きく影響されています。この原理は、私たちが物事を比較し、対照的な特性によってそれらを区別する傾向を指します。
そして、この原理はマーケティングや営業の現場でも活用されています。では、具体的にどのように活用され、私たちの選択にどのように影響を与えるのでしょうか。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
コントラストの原理とは
二つ以上の異なる刺激を比較し、その違いを通じて各刺激を理解するという人間の傾向のこと
心理学におけるコントラストの原理は、我々が物事を評価し、理解する方法に関連しています。この原理は、我々が物事を比較し、対照的な特性によってそれらを区別する傾向があるという考えに基づいています。
以下に、心理学におけるコントラストの原理のいくつかの主要な側面を詳しく説明します。
これらの原理は、我々が世界をどのように認識し、理解し、反応するかに深く関与しています。それらは、心理学、マーケティング、広告など、多くの分野で応用されています。
コントラストの原理の具体例
ではここからは、コントラストの原理の日常的な事例をいくつか紹介していきます。
- ショッピング
- 食事
- 感情
事例1:ショッピング
店頭やオンラインショップで商品を比較するとき、コントラストの原理が働きます。例えば、高価な商品と安価な商品が並んでいると、安価な商品はさらにお得に感じられるでしょう。また、セールの際には、元の価格と割引後の価格を比較することで、節約した感じが強まります。
事例2:食事
食事の際にもコントラストの原理が働きます。例えば、甘いデザートを食べた後に飲むコーヒーは、より苦く感じられるでしょう。また、辛い料理の後に食べるヨーグルトは、より爽やかに感じられます。
事例3:感情
感情的な体験においてもコントラストの原理が働きます。例えば、困難な状況を経験した後の成功は、より満足感を与えます。また、悲しい出来事の後に起こる喜びは、より強く感じられるでしょう。
コントラストの原理が発動する理由
ではここからは、コントラストの原理が発動する心理学的、脳科学的理由を解説します。
- 感覚処理
- 認知処理
理由1:感覚処理
コントラストの原理は、我々が物理的な刺激をどのように認識するかに関連しています。例えば、視覚的なコントラストは、視覚野のニューロンが活動する方法に基づいています。これらのニューロンは、明るさや色の違いを検出することで、物体やパターンを識別します。明るい色は暗い背景に対してより鮮やかに見え、大きな物体は小さな物体の近くにあるときにより大きく見えます。これは、脳が相対的な違いを強調し、情報をより効率的に処理するための方法です。
理由2:認知処理
コントラストの原理はまた、我々が情報を理解し、意思決定を行う方法にも関連しています。これは、脳の前頭葉と特に前頭前皮質が関与する認知的なプロセスに基づいています。これらの領域は、情報を評価し、比較し、選択を行う役割を果たします。例えば、高価な商品と安価な商品を比較すると、安価な商品はよりお得に感じられます。これは、脳が相対的な価値を評価し、最善の選択を行うための方法です。
コントラストの原理を営業・マーケティングに活用する方法
ではここからは、コントラストの原理を営業やマーケティングに活用する方法をいくつか紹介します。
- 価格設定
- 商品の表示
- 使用の前後
- 競合他社
- ボタンの設置
方法1:価格設定

コントラストの原理を利用して商品の価格を設定することで、消費者に商品の価値を強調することができます。例えば、高価な商品と安価な商品を並べることで、安価な商品はさらにお得に感じられるでしょう。また、元の価格と割引後の価格を表示することで、消費者は節約した感じが強まります。ちなみに、上記画像は、ウーバーサジェストというSEOツールの価格表示になります。
方法2:商品の表示
商品の表示方法によっても、コントラストの原理を利用することができます。例えば、新商品を既存の商品と比較して強調することで、新商品の特徴や利点を強調することができます。また、商品の色、サイズ、形状などの視覚的な要素を対照的にすることで、商品を目立たせ、消費者の注意を引くことができます。
方法3:使用の前後
コントラストの原理を利用して、商品の使用前と使用後を比較することで、その効果を強調することができます。例えば、スキンケア製品の広告では、使用前と使用後の肌の状態を比較することで、製品の効果を強調します。また、ダイエット製品の広告では、使用前と使用後の体型の変化を比較することで、製品の効果を強調します。これらの比較は、消費者に製品の具体的な利益を示し、購入意欲を刺激します。
方法4:競合他社
コントラストの原理を利用して、自社の商品と競合他社の商品を比較することで、自社の商品の優位性を強調することができます。例えば、自社の商品が競合他社の商品よりも高品質である、より安価である、より独自の特徴を持っているなどの点を強調することができます。このような比較は、消費者に自社の商品の価値を示し、選択を促します。
方法5:ボタンの設置
CTAとは、「Call To Action」の略で「行動要請」を意味します。つまり、こちらがユーザーに取ってもらいたいアクションを要求することです。たとえば、ケース1とケース2では、クリック率に大きな変化が生まれます。というのも、ケース一1の場合は、コントラストの原理により「問い合わせるよりはいっかぁ〜」ということで、資料の請求率が高まりますが、ケース2では、比較する対象が存在しないので、離脱に繋がってしまう可能性が高くなるからです。
まとめ
コントラストの原理:高いを安いに変える魔法の心理法則
コントラストの原理は、私たちが物事を評価し、理解する方法に深く関わっています。感覚的なコントラスト、感情的なコントラスト、認知的なコントラストという三つの側面から私たちの認知と行動に影響を与えます。
また、この原理はマーケティングや営業の現場で、価格設定、商品の表示、使用の前後の比較、競合他社との比較、ボタンの設置など、様々な方法で活用されています。これらの活用法を理解し、適切に利用することで、消費者の選択を効果的に導くことが可能となります。
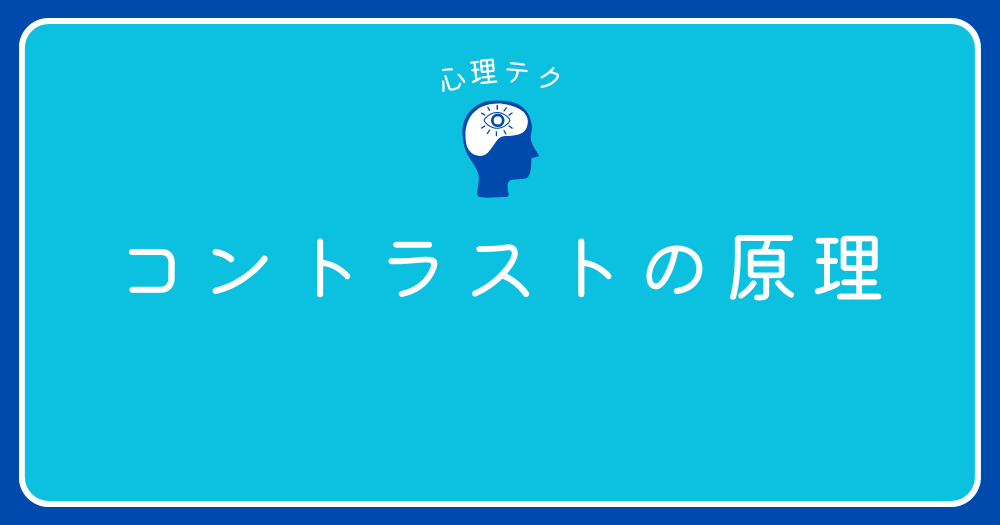
-1.jpg)

コントラストの原理:高いを安いに変える魔法の心理法則