アフォーダンスとは、環境と人間(あるいは動物)の相互作用を扱う理論のことです。
たとえば、ドアノブ(モノ)が付いているドアがあったとする。これにより我々は今までの経験から「このドアはノブをひねって開けるんだ!」と瞬時に行動に起こすことができます。このように、世の中は、モノがアフォード(提供)したものを、我々がピックアップ(受け取る)するという関係で成り立っているのです。
しかし、アフォーダンス理論を学ぶことで、どんなメリットがあるのでしょうか。本記事では、アフォーダンス理論への深い理解を最大の目的とすると共に、さらにはマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
アフォーダンス理論とは
環境と人間(あるいは動物)の相互作用を扱う理論
アフォーダンス理論とは、心理学者ジェームズ・J・ギブソンによって提唱された、環境と人間(あるいは動物)の相互作用を扱う理論です。アフォーダンスは、環境が提供する行動の可能性や機会を指します。これは、個体が環境の中で自然に行いたくなる行動や、環境が促す行動のことを言います。
例えば、椅子は座ることを促すアフォーダンスを持っています。それは、椅子の形状や構造が人間の体に合った形で作られているため、座ることが自然にできるようになっています。このように、アフォーダンス理論は、環境がどのようにして私たちの行動を誘導し、私たちがどのように環境に適応して行動するかを説明するものです。
アフォーダンス理論は、デザインや人間工学、心理学など様々な分野で応用されています。例えば、デザインの分野では、製品やインターフェースがどのように使われるべきかをユーザーに示すためにアフォーダンスを利用します。この理論によって、人々が直感的に使いやすい製品を開発することが可能になります。
アフォーダンス理論の具体例

では、ここからはアフォーダンス理論の具体例を少し多めに見ていきましょう。というのも、アフォーダンス理論は、心理学初心者には難しい理論となっているからです。様々な事例を見て行くことで、さらに理解を深めていきましょう。
- ドアノブ
- スイッチ
- 滑り台
- カップの取っ手
- スマートフォンのスクリーン
事例1:ドアノブ
ドアノブは、ドアを開けるために回すことを促すアフォーダンスを持っています。ドアノブの形状が手にフィットするように設計されており、人々は自然に回す動作を行います。
事例2:スイッチ
電気のスイッチは、オン・オフを切り替えるためのアフォーダンスを持っています。スイッチの形状や配置が指で押すことを容易にし、明示的な指示がなくても直感的に使い方がわかります。
事例3:滑り台
遊び場の滑り台は、子どもたちに滑ることを促すアフォーダンスを持っています。滑り台の形状が滑る動作を自然に引き出し、子どもたちは遊び方をすぐに理解できます。
事例4:カップの取っ手
カップの取っ手は、持ち上げることを促すアフォーダンスを持っています。取っ手の形状が指にフィットし、カップを持ち上げる動作が自然に行えるようになっています。
事例5:スマートフォンのスクリーン
スマートフォンのタッチスクリーンは、画面をタッチして操作することを促すアフォーダンスを持っています。画面上のアイコンやボタンが指でタッチすることを容易にし、直感的な操作が可能になります。
アフォーダンス理論とシグニフィア
アフォーダンス理論とシグニファイア(signifier)は、どちらもデザインや環境と人間のインタラクションに関する概念ですが、異なる視点から解釈されています。事例を用いて、それぞれの違いを説明します。
事例:アフォーダンス理論
アフォーダンス理論は、環境やオブジェクトが持つ機能や使い方を示す性質を指します。アフォーダンスは、オブジェクト自体が持つ形状や構造から生じる直感的な使い方を意味します。
たとえば、ドアノブ ドアノブは、手で握りやすい形状があり、回すことでドアが開くアフォーダンスを持っています。このため、人々はドアノブの存在から自然にドアを開ける方法がわかります。
事例2:シグニフィア
一方、シグニファイア(signifier)は、アフォーダンスを視覚的に示す手がかりや記号を指します。シグニファイアは、デザインや環境において、どのようにアクションを行うべきかを示す目に見えるサインです。
たとえば、ドアのプッシュ・プルサイン ドアには、どちらの方向に動かすべきかを示す「プッシュ」(押す)や「プル」(引く)といったサインがあります。これらのサインはシグニファイアであり、ドアの使い方を視覚的に伝える役割があります。
要するに、アフォーダンスはオブジェクト自体が持つ使い方を示す性質であり、シグニファイアはそのアフォーダンスを人々に伝えるための視覚的な手がかりや記号です。両者は、デザインや環境と人間のインタラクションに関して相互に関連していますが、異なる概念として捉えられています。
アフォーダンス理論をマーケティングに活用する方法
では、ここからはアフォーダンス理論をマーケティングに活用する方法をいくつか紹介します。
- ウェブサイトやアプリのデザイン
- 商品パッケージデザイン
- 効果的なCTA
方法1:ウェブサイトやアプリのデザイン
アフォーダンス理論をウェブサイトやアプリのデザインに活用することで、ユーザーが直感的に操作できるインターフェースを実現できます。
例えば、シンプルなナビゲーションメニューやユーザーフレンドリーなフォームデザインを採用することで、顧客はサイト内での目的の達成がしやすくなります。フォームデザインで言えば、入力情報を横に広げた形ではなく、縦に表示させることで入力完了率を高めることが可能です。
方法2:商品パッケージデザイン
アフォーダンス理論を商品パッケージデザインに取り入れることで、顧客が商品の使い方や利点を直感的に理解しやすくなります。
例えば、Heinzのケチャップボトルでは、逆さに置くことができるデザインが導入されており、ケチャップを簡単に出すことができます。これにより、顧客は商品の使いやすさを実感し、リピート購入や口コミでの評判が広がります。
方法3:効果的なCTA
アフォーダンス理論を活用したマーケティングでは、シンプルで効果的なコールトゥアクション(CTA)を設定することが重要です。CTAは、顧客に特定のアクションを促すための明確な指示やボタンです。
例えば、購入を促すCTAとして、「今すぐ購入する」「カートに追加する」といったボタンを目立つ位置に配置することで、顧客は直感的に購買行動を起こしやすくなります。CTAのデザインや文言にも注意し、顧客に直感的にアクションを起こせるような設計を心掛けましょう。
まとめ
アフォーダンス理論とは|意味・具体例・活用法を解説
アフォーダンス理論は、消費者を誘導する上で非常に大切な理論です。
初めてアフォーダンス理論を知った人は少し理解に苦しむところもあるかもですが、一度理解できるとあなたの売上を爆増させてくれます。
なので、理解できるまで、何度も繰り返しこの記事を読んで、あなたの仕事に活用していきましょう。
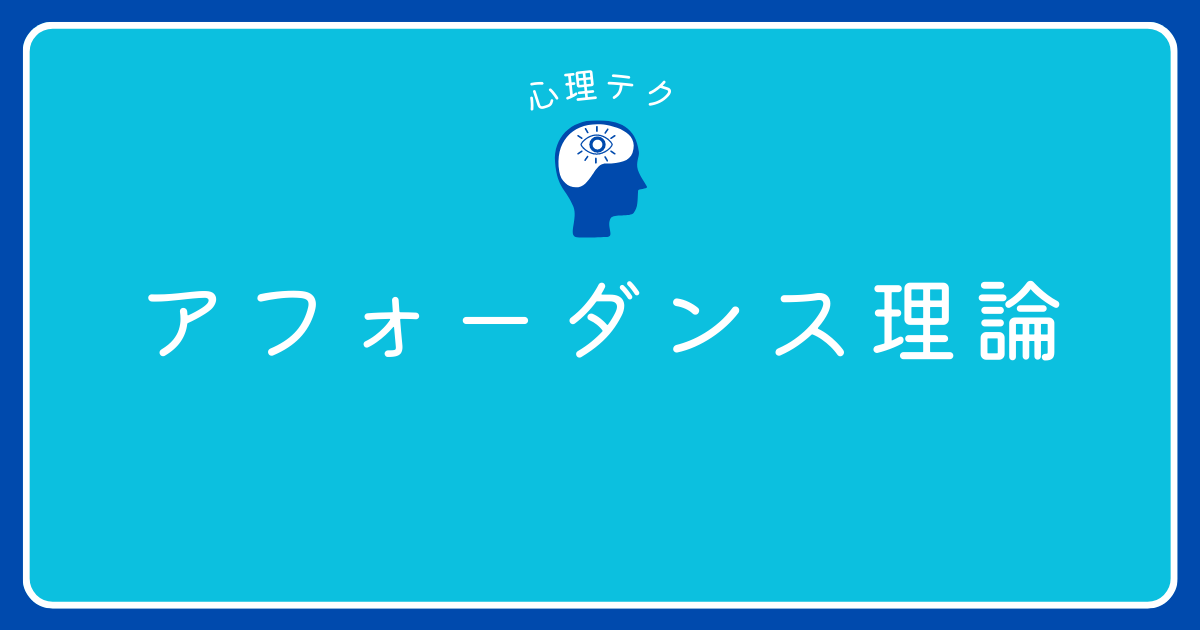
-1.jpg)



アフォーダンス理論とは|意味・具体例・活用法を解説