権威性の法則とは、専門家の意見に従いやすくなるという心理傾向のことです。
たとえば、お医者さんから出された薬を、わざわざ疑うなんてことはしないですよね?他にも、「ペンシルバニア大学の研究で〜」なんて言われたら、その内容がどうであれ、ちょっと納得してしまいますよね。
このように、我々は専門家からの意見に従いやすいという本能が備わっています。この記事では、権威性を獲得する方法、営業やマーケティングに活用する方法などについて詳しく解説していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
権威性の法則とは
専門家の意見に従いやすくなるという心理傾向
別の言い方をすると、「専門家の意見に盲目的になりやすいという心理法則」ですね。これは権威を持つとされる人々が専門知識や経験を持っていると考えられるため、その意見や判断が正しいと信じやすくなります。
例えば、医師がある薬を処方した場合、患者はその薬が自分の病気に効果的であると信じる傾向があります。同様に、教授や専門家がある事柄について意見を述べると、その意見が正しいと考えられる可能性が高まります。
権威性の法則を理解し、適切に活用することで、他人を説得したり、自分の信頼性を高めることができます。ただし、権威性の法則を利用して誤った情報を広めたり、他人を操るような行為は、もちろん、倫理的に問題があります。
権威性の法則の具体例
ではここからは、権威性の法則の日常的な事例をいくつか紹介します。
- 医師の指示に従う
- 教師の教えに従う
- ニュースや報道に従う
事例1:医師の指示に従う
患者は、医師が専門家であると信じているため、処方された薬や治療法に従いがちです。権威性の法則により、患者は医師の意見や指示を疑うことなく、その指示に従うことが多いです。
事例2:教師の教えに従う
学生は、教師がその分野の専門家であると信じているため、教師の指示や教えに従います。教師の権威性によって、学生は教師が伝える情報や知識を受け入れやすくなります。
事例3:ニュースや報道に従う
人々は、報道機関や専門家が提供する情報に基づいて意見を形成し、行動することが多いです。報道機関や専門家が権威性を持っていると信じられているため、その情報や意見に従いがちです。
権威性の法則はなぜ発動するのか
では、ここからは、権威性の法則が働く理由について解説していきます。
我々の脳は「専門家=正しい」という直感的な判断するという性質を持っています。なぜなら、このような直感的な判断をすることで、脳のエネルギー(意志力)を節約することができるからです。
もっと簡単に言うと、全てのことに思考していたら、脳がバーストしてしまうからです。たとえば、下記のようなことを考えて、いちいち行動しないですよね。
- 朝起きたが、歯を磨くべきだろうか?
- 今日は〇〇線を使って出社するべきだろうか?
- 今日はお風呂に入るべきだろうか?
このように、脳は、頻繁に繰り返す思考・行動に関しては、思考をショートカットするようにできています。これを我々は、”習慣化”と呼びます。
これは権威性の法則も一緒です。たとえば、何度も紹介している通り、お医者さんに対して「この人の処方してくれた薬は大丈夫だろうか?」なんて思わないですよね。
権威性の法則の実験

スタンレー・ミニグラム氏は、人道的にどうなのか、と疑われるような、おぞましい実験を行いました。まず、被験者たちは「罰が学習に与える影響を調べる」という名目で実験に集められ、研究者たち(権威)は、被験者を下記の2つのグループに分けました。
- 学習者役(問題に答える)
- 教師役(学習者が問題を違ったら罰を与える)
次に、学習者役は、電気椅子に固定され、教師役が出す問題に答えていきます。一方、教師役は学習者役が問題を間違うごとに電圧を上げて電流を流すという仕事を任されます。
(※一問、間違うごとに15ボルトづつ電流を上げていき、最大で450ボルトまで上げます)
もちろん、教師役はビクビクしながら、学習者役が問題を間違うごとに電流を流します。電流を流された学習者役の声は、電圧を上げるごとにどんどん大きくなり「もうやめてくれ!!!」と大声をあげるほどでした。
実は、学習者役の被験者は、ミニグラムに雇われたサクラでした。つまり、学習者役は電流を流され、苦しんでいる演技をしていただけだったのです
学習者役の叫び声は、インターホン越しに教師役に伝わります。しかし、研究者たち(権威)は教師役に「これは許可を取っていて大切な実験なので、躊躇なく電流を流してください」と伝えます。そのときに、どれくらいの教師役の人たちが、この研究者たちに服従するか?ということを調べました。
結果、最大の450ボルトまで電圧を上げた教師役は、全体の65%までにのぼりました。さらに、40名の被験者のほとんどが、この実験を途中で投げ出さなかったというのには驚きです。つまり、被験者のほとんどが、権威の前で盲目的になってしまったということですね。
権威性の法則を営業、マーケティングに活用する方法
では、権威性の法則を営業、マーケティングに活用する方法をいくつか紹介しますね。
- 服装
- 専門知識
- 経歴
- 話し方
- 資格
- 書籍
- 推薦状
方法1:服装
服装の力については、これまでに繰り返しお伝えしてきました。医者であるなら、白衣をまとうのは当然でしょう。
では、営業マンは?と言えば、もちろんスーツですね。最近では、スーツを着ない営業マンも増えてきてはいますが、完全に私服というのは、権威性を活かしきれていない営業戦略になります。なので、カジュアルでもいいので、営業中はスーツを着ることを意識してみてください。
方法2:専門知識
あなたが営業マンで、電気自動車(EV)の販売を担当しているとしましょう。
この場合、電気自動車の性能や環境への利点に関する専門知識を顧客に提供することで、あなた自身やあなたの会社の権威性を高めることができます。顧客に最新の研究や業界の動向を説明し、彼らがより良い購入判断を下せるようにサポートすることで、信頼性が高まります。
方法3:経歴
自分や会社の経歴、実績、肩書きを強調し、業界における経験と専門知識をアピールすることで、顧客に信頼される権威者として認識されることができます。
方法4:話し方
実は、ちょっと話し方を変えるだけで、あなたの権威性を高めることができます。
それは、理由を添えるというもの。何かの主張をしたら、「なぜなら〜」という形で理由を説明するようにしましょう。実は、理由を添えることで、説得力が高まるということが分かっています。下記にPREP法というフレームワークを使った文章を紹介しておきますね。
- Point (主張): 弊社のCRMソフトウェアは、顧客対応の効率化に効果的です。
- Reason (理由): なぜなら、これは弊社のCRMソフトウェアが顧客情報の一元管理を可能にし、営業チームが簡単に顧客履歴やニーズを把握できるからです。
- Example (具体例): 例えば、A社は弊社のCRMソフトウェアを導入した結果、顧客対応時間を30%短縮し、営業成約率が20%向上しました。
- Point (主張): なので、弊社のCRMソフトウェアを導入することで、あなたの会社も顧客対応の効率化を実現できます。
方法5:資格
営業マンが専門的な資格を持っていることをアピールすることで、顧客に対して自分たちが専門知識を持っていると証明できます。
たとえば、経営コンサルタントなら中小企業診断士、保険の営業であればFP検定、不動産営業なら宅建士など。顧客からしたら、どれだけすごいか分からないということもありますが、「国家資格」などの説明をすることで、より権威性を高めることができます。
ちなみに、オータニは、”心理学×営業”というポジションで権威を取りたかったので、念の為「心理学検定特1級」という資格を取得しました。
方法6:書籍
書籍を出しているというだけで、権威を獲得することができるようになります。
もし、お金があるのであれば、自費出版するのもありですね。というのも、お金を出すだけで、簡単に権威を獲得することができるからです。つまり、「本を出版しています」と伝えることができるからです。自費出版だったとしても、権威性が高まるので、投資対効果としては悪くない選択なのではないでしょうか。
方法7:推薦状
営業において、既存の顧客からの推薦や成功事例を活用することで、権威性を高めることができます。
例えば、あなたがITソリューションの営業をしている場合、過去の顧客からの感謝の声や成功事例を紹介することで、新しい顧客に対してあなたの会社が信頼できるパートナーであることを示すことができます。
他にも、インフルエンサーマーケティングも、推薦状と言えるでしょう。たとえば、YouTuberなどの、影響力のある人物に商品を紹介してもらうことで、効果的に集客を行うことができるようになります。
まとめ
権威性の法則とは|実績ゼロでも誘導できる最強の心理学
権威性の法則は、瞬時に相手を従わせることが出来る最強の心理法則です。
もし、本記事ですぐにでも使えそうなものがあれば、すぐにでもあなたの営業戦略に導入するようにしましょう。
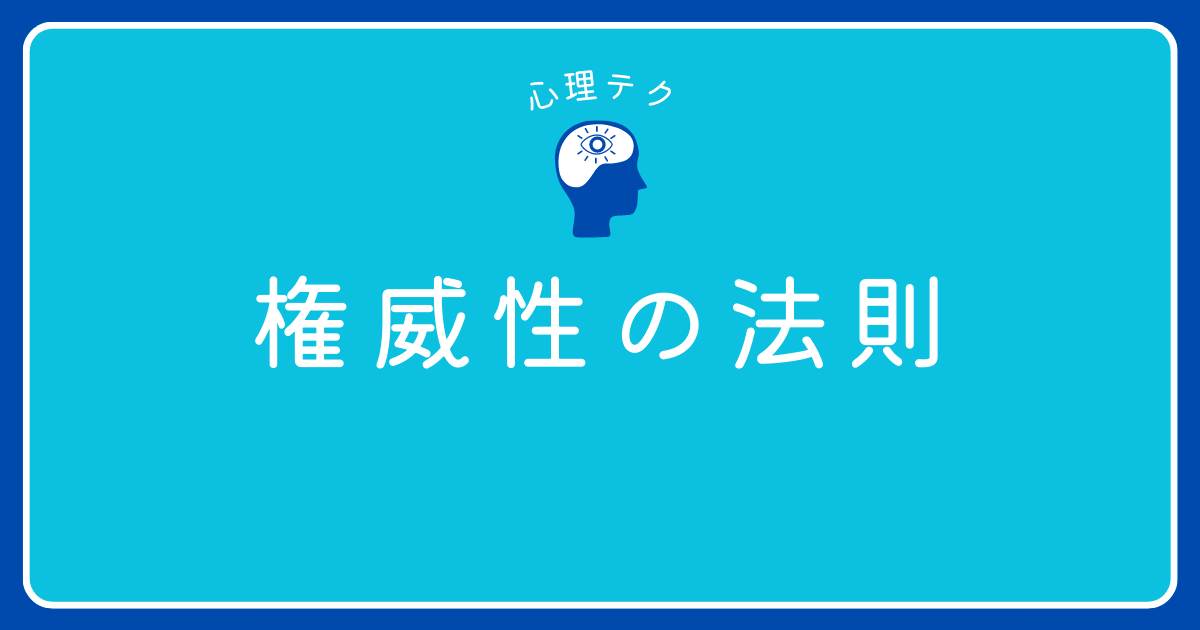
-1.jpg)

権威性の法則とは|実績ゼロでも誘導できる最強の心理学