- 片面提示とは、ある対象のメリット(またはデメリット)だけを伝える説得術
- 両面提示とは、ある対象のメリットとデメリットの両方を伝える説得術
営業・交渉などでは、これらを使い分けることで、相手を効果的に説得することができるようになります。
というわけで、本日は
- 片面提示とは
- 両面提示とは
- 片面提示と両面提示を使い分け方
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
片面提示とは
ある対象のメリット(またはデメリット)だけを伝える説得術
両面提示を理解するには、まず片面提示から理解すると良いでしょう。というわけで、便宜上、まずは片面提示から詳しくみていきましょう。
片面提示の例
- こちらの商品は、非常に性能が充実しています
- この薬を飲むことで、痛みを軽減させることができます
- A店が出すパスタは絶品です
デメリット
片面提示では、気をつけなければならないことがあります。それは、信頼の無い人に対して使うと、胡散臭いと判断されてしまうことです。これは信頼を失墜させる原因にもなりえます。
たとえば、初めて会った営業マンから、「この商品は〜なところが良くて、〜なところが最高なんです!」と伝えられても、「それは営業マンだから、良いことしか言わないよね…」と感じてしまいます。
両面提示とは
ある対象のメリットとデメリットの両方を伝える説得術
両面提示の例
- 重量感は増えましたが、こちらの商品は、非常に性能が充実しています
- 〇〇という副作用はありますが、この薬を飲むことで、痛みを軽減させることができます
- ちょっと値段は高いですが、A店が出すパスタは絶品です
両面提示の実験
社会心理学者の林理さん、山岡和枝さんは、生命保険の広告を題材に、被験者の大学生に対して、下記の2つの広告を提示しました。
- リスクを提示しない広告(片面提示)
- リスクも提示した広告(両面提示)
そして、それぞれの広告に「どれくらい好感をもったか?」を聞きました。結果、80%の大学生は、リスクも提示した広告(両面提示)に好感を示しました。
このように、デメリットと一緒にデメリットも同時に提示された方が、信頼が生まれそれが高感度を高めるようです。
メリット
両面提示のメリットとしては、信頼の無い人に対して使うと、逆に信頼を獲得することができるところです。
なぜなら、メリットと一緒にデメリットを伝えることで、「この人は、わざわざ言う必要がないデメリットまで伝えてくれている!信用できる!」という感じで信頼を得ることができるからです。
例:営業
たとえば、初めて会った営業マンから、メリットだけを伝えられても、ちょっと信じられないですよね?
なぜなら、「まぁそりゃ営業マンだし、良いところしか言わないよね〜」となるからです。
しかし、あえてデメリットも一緒に伝えることで、信頼関係を強固にすることができるようになります。
両面提示で意識するべき2つのポイント
両面提示を行う際は、下記の2つのことを意識するようにしましょう。
- メリットとデメリットの関係性
- メリットとデメリットの順番
ポイント1:メリットとデメリットの関係性
メリットとデメリットの間に、しっかりとした関係性を持たせましょう。
たとえば、「ちょっと値段は高いですが(デメリット)、A店が出すパスタは絶品です(メリット)」という感じで。
このように、「値段が高い→絶品」のようにメリットとデメリットの間に相関関係があれば問題ありません。
悪い例としては、「ちょっとここから1時間ほど離れているのですが(デメリット)、A店の出すパスタは絶品です(メリット)」という感じですね。
このように、「距離が離れてる→絶品」のようにメリットとデメリットの間に相関関係がなければ両面提示は効果を発揮しません。
実験:社会科学者ゲルト・ボーナー
ボーナーたちは、あるレストランの広告を3種類作りました。
- メリットだけを載せた(「くつろいだ気分を〜」)
- 繋がりが無いメリットとデメリットを載せた(「店内はくつろいだ雰囲気ですが、専用駐車場はありません」)
- 繋がりが有るメリットとデメリットを載せた(「当店は狭いですが、くつろいだ雰囲気です」)
そして、それぞれのグループの被験者が、どの広告を評価するか?を観察しました。
結果、2種類の両面体なメッセージは、共にレストランのオーナーへの信用を向上させましたが、レストランの評価が最も高かったのは③という結果となったのです。
このように、メリットとデメリットの間には関係性がないと、効果は最大化しないということが分かりますね。
ポイント2:両面提示の順番
両面提示の際は、デメリット→メリットという順番で伝えるようにしましょう。
理由としては、下記の2つの心理法則が働くからです。
- 新近効果
- コントラストの原理
理由1:新近効果
最後の印象が記憶に残りやすいという心理現象
もし「メリット→デメリット」という順番で提示してしまうと、「デメリット」が記憶に強化されてしまうわけです。だから、必ず「デメリット」から伝えるようにしましょう。
- 重量感は増えましたが、こちらの商品は、非常に性能が充実しています
- 〇〇という副作用はありますが、この薬を飲むことで、痛みを軽減させることができます
- ちょっと値段は高いですが、A店が出すパスタは絶品です
理由2:コントラストの原理
先行刺激によって、行動の刺激が歪められて認知されてしまうという心理現象
たとえば、先に5キロの荷物を持つよりも、10キロの荷物を持ってからの方が5キロの荷物が軽く感じますよね?
つまり、「デメリット→メリット」という順番で提示することで、メリットだけを伝えた時より、メリットの部分がより強調されるわけです。
さらにいうと、小さなデメリットを伝えて、大きなメリットを伝えると、メリットの部分が最大化されるので、オススメです。
まとめ
片面提示と両面提示|交渉を有利にする心理学
「デメリットを伝えると、交渉に失敗する可能性が高まるのでは!?」というのはただの勘違いです。
むしろ、デメリットも一緒に伝えた方が、信頼関係も強固になりますし、交渉後のトラブルも激減します。
なので、デメリットを包み隠していた方は、ぜひ積極的にデメリットを伝える交渉をするようにしましょう。
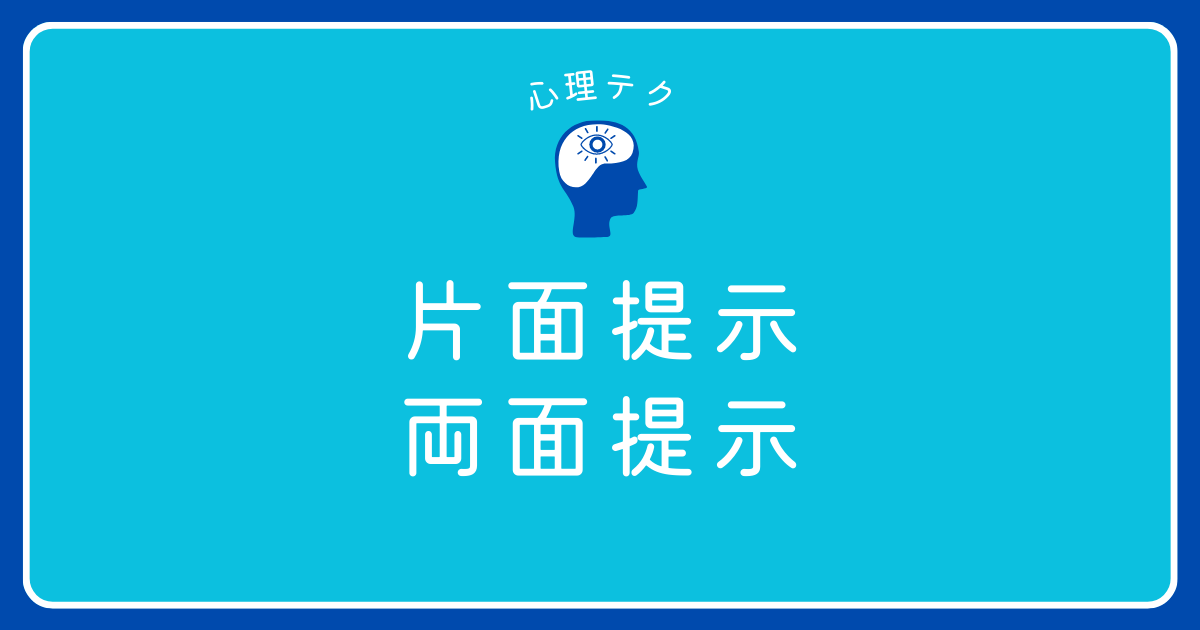
-1.jpg)
