誤前提暗示(ごぜんていあんじ)とは、質問そのものに含まれる前提を受け入れるように誘導する手法のことです。
たとえば、好きな女性をデートに誘う時、「今度、デートしない?」と誘うよりも「今度、ランチかディナーに行かない?」と誘った方が、デートにいける可能性が高まるのです。このように、ただ要求するのではなく、二者択一の質問によって要求した方が、その承諾率が高まるのです。
しかし、なぜこのような現象が起こるのでしょうか。本記事では、誤前提暗示の心理学的メカニズムやこれを営業やマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
誤前提暗示とは
質問そのものに含まれる前提を受け入れるように誘導する手法のことです
誤前提暗示とは、質問の形をとりながら、一定の前提を含んだ論理的誤謬です。この種の質問は、質問そのものが受け取り手に一定の前提を強制的に受け入れさせ、その前提に基づいて回答を求めます。
たとえば、”あなたはまだその嘘をつき続けていますか?”という質問は誤前提暗示の一例です。この質問は、回答者が以前に嘘をついたという前提を含んでおり、”はい”または”いいえ”で回答すると、どちらの場合も回答者が嘘をついたことを認める形になります。
誤前提暗示は、しばしば、議論や対話を不公平にする手段として用いられます。このような質問は通常、回答者が自己防衛のために前提自体を否定することを余儀なくされる状況を作り出します。これは、対話の本来の目的である真実を明らかにし、理解を深めるという目的から外れたものです。
誤前提暗示の具体例
では、いくつか具体例をみていきましょう。
- “あなたはまだジャンクフードばかり食べているのですか?”
- “あなたの新しい仕事はいまだに厳しいですか?”
- “あなたはまた遅刻してきましたか?”
事例1:”あなたはまだジャンクフードばかり食べているのですか?”
この質問の前提は、「あなたは以前ジャンクフードばかり食べていた」です。この質問に「はい」または「いいえ」で答えることは、その前提を受け入れることを意味します。つまり、回答者が以前ジャンクフードばかり食べていたという事実を認めることになります。
事例2:“あなたの新しい仕事はいまだに厳しいですか?”
この質問の前提は、「あなたの新しい仕事は厳しい」です。回答者がこの質問に「はい」または「いいえ」で答えると、その前提(新しい仕事が厳しいという事実)を受け入れることになります。
事例3:“あなたはまた遅刻してきましたか?”
この質問の前提は、「あなたは以前に遅刻した」です。回答者がこの質問に「はい」または「いいえ」で答えると、その前提(遅刻したという事実)を受け入れることになります。
誤前提暗示はなぜ発動するのか
ではここからは、誤前提暗示が発動する心理学的理由について解説していきます。
- 質問の前提に対する自動的な受け入れ
- 社会的な期待と規範
- 認知的な負荷
理由1:質問の前提に対する自動的な受け入れ
人間は、質問が提出されると自動的にその前提を受け入れる傾向があります。これは、私たちが日常的に質問に答えるときの基本的な通信パターンによるもので、通常は有益で効率的な方法です。しかし、これが誤前提暗示の力を増幅させる一因となります。
理由2:社会的な期待と規範
社会的なコミュニケーションでは、質問に対して直接的で簡潔な回答を提供することが期待されます。これは、特に二者択一の質問(「はい」または「いいえ」で答える質問)に対しては特に強いです。そのため、誤前提を否定するために質問の形式を破ることは、コミュニケーションの規範に反すると感じられます。
理由3:認知的な負荷
誤前提を認識し、それに対抗するには、意識的な思考とエネルギーが必要です。多くの人々は、特にプレッシャーの下では、この追加の認知的な負荷を避ける傾向があります。これは、質問の前提を無批判に受け入れることを促します。
誤前提暗示のポイント
誤前提暗示は、しばしば議論や説得の文脈で利用される戦略ですが、その使用は注意が必要です。誤解を招く可能性があり、不公正な議論手法と見なされることもあるためです。それでも、適切に用いる場合のポイントをいくつか挙げてみましょう。
- 適切な前提を設定する
- 二者択一の形式を用いる
- 選ばせたい選択肢は最後に
- 質問を自然に見せる
ポイント1:適切な前提を設定する
誤前提暗示の強力さは、その質問が含む前提に大きく依存します。前提は、聞き手が受け入れる可能性が高いものでなければならず、その情報に関する既存の信念や知識に適合するものでなければなりません。
ポイント2:二者択一の形式を用いる
「はい」または「いいえ」で回答する形式の質問は、特に誤前提暗示に効果的です。これは、聞き手が質問の前提を受け入れるか、それを否定するかの二つの選択肢しか提供しないためです。
ポイント3:選ばせたい選択肢は最後に
二者択一で選択をさせる時、相手に選ばせたいものを後ろに持っていくようにしましょう。なぜなら、我々には、後ろの情報の方がインパクトに残りやすいという性質があるからです。これを新近効果といいます。
たとえば、ヒトラーの大衆煽動の例を挙げると、彼は下記のような感じで聴衆に質問を投げかけていました。
このように、「皆殺し!」を選択させたい場合は、そのメッセージを後ろに持ってくると大衆はそれを選択しやすくなるのです。
ポイント4:質問を自然に見せる
誤前提暗示が効果的に機能するためには、その質問が自然で、普通の会話の一部として流れるように見える必要があります。質問が強制的や不自然に見えると、聞き手がその前提を疑問視し、誤前提を拒否する可能性が高まります。
誤前提暗示を営業での活用事例
ではここからは、誤前提暗示を営業に活用した事例をいくつか紹介します。
- 予算の質問
- 製品の購入時期の提案
- 追加オプションの提案
- 支払い方法の提案-1
- 支払い方法の提案-2
事例1:予算の質問
「以上で弊社サービスの説明は終わりになりますが、ご予算の方はいかがでしょうか?」
この質問の前提は、顧客が製品を購入するというもので、予算が合えば購入するという前提条件を受け入れていることになります。
事例2:製品の購入時期
「あなたは今週中に注文を出しますか、それとも来週中に注文を出しますか?」
この質問は、「あなたは注文を出しますか?」よりも効果的です。なぜなら、前者の質問の前提は顧客が注文を出すというもので、その選択肢は「今週中に出す」か「来週中に出す」かとなります。
事例3:追加オプションの提案
「高級な革製シートを追加しますか、それとも純正にいたしますか?」
この質問の前提は、顧客が何らかの追加オプションを選ぶというもので、その選択肢は「高級な革製シートにする」か「純正のものにする」かとなります。
事例4:支払い方法の提案-1
「お支払いはクレジットか、現金のどちらになさいますか?」
この質問の前提は、顧客が製品を購入するというもので、その選択肢は「クレジットを選ぶ」か「現金を選ぶ」かとなります。
事例5:支払い方法の提案-2
「お支払いは一括にいたしますか、それとも分割払いにいたしますか」
この質問の前提は、顧客が製品を購入するというもので、その選択肢は「今すぐ全額支払う」か「分割払いを選ぶ」かとなります。
誤前提暗示をマーケティングでの活用事例
ではここからは、誤前提暗示をマーケティングに活用した事例をいくつか紹介します。
- 2択のコピー
- ボタンを2つ設置する
方法1:2択のコピー
「あなたは、オンライン講座を受講しますか、それともオンラインサロンへ参加いたしますか?」
もし、フロントエンド商品が2つ以上あるのであれば、前のようなコピーを用いることで、リスト獲得を実現させることができるようになります。お気づきの通り、こちらの理屈にしては、営業での活用のそれと全く一緒になります。
方法2:ボタンを2つ設置する
このように、2つのボタンを設置することで、どちらからのボタンのCTRを高めることが可能になります。仮に1つのボタンしかなかった場合、そのボタンのCTRが、2択の時よりも低下してしまうことがあります。なので、CTRを高めたいのであれば、必ずボタンは2つ用意することを忘れないようにしましょう。
まとめ
誤前提暗示とは|「YES」の確率を高める説得術
誤前提暗示は、言葉の魔術師たちの間で一般的に使用される心理学的なテクニックの一つです。このテクニックは、特定の前提を暗黙的に受け入れさせることで、相手の反応や行動を誘導します。日常的な会話、営業、マーケティングなど、さまざまな場面で効果的に活用していくようにしましょう。
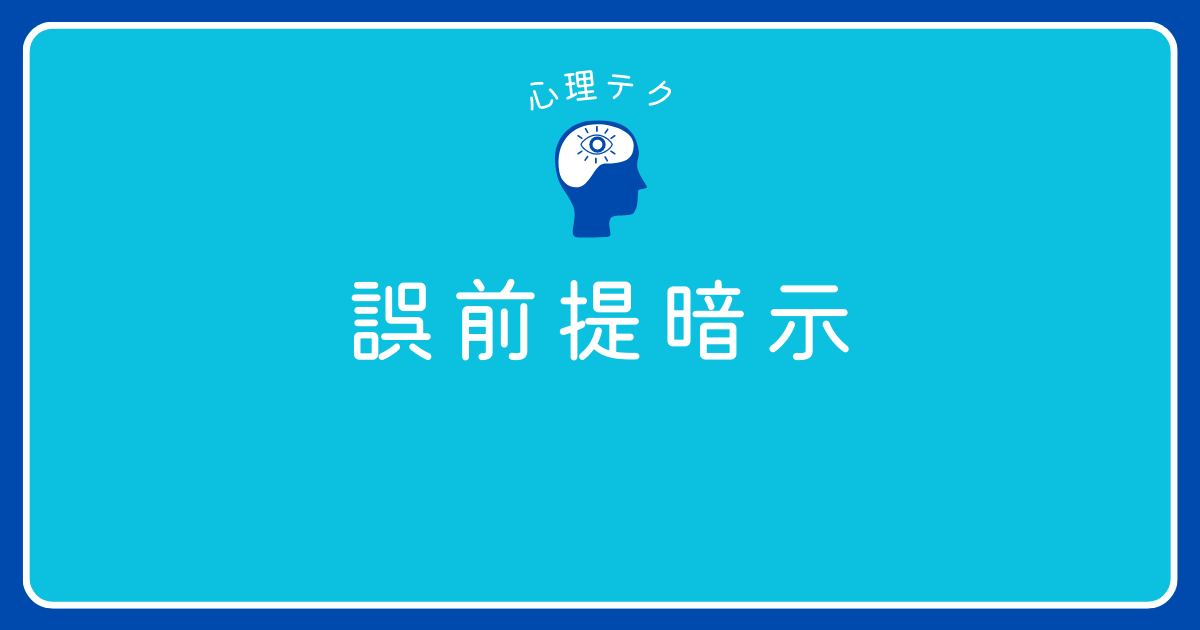
-1.jpg)

誤前提暗示とは|「YES」の確率を高める説得術