プラシーボ効果(placebo effect)とは、「思い込みの力」によって、人間の身体・精神に影響を与える心理現象のことです。
たとえば、「本当の薬」だと思い込ませて、「偽薬」を飲まされると痛みを感じなくなったりなどという事例があったり、他にも「お酒」だと思い込んで「アルコール0の飲料」を飲むと酔っぱらってしまったりなど。
「思い込みの力」ってすごいですよね。このように、我々は思い込むことにより、身体や精神が思わぬ影響を受けることがあります。
しかし、なぜこのような現象が起こるのでしょうか。本記事ではプラシーボ効果が発動する心理学的理由やマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
プラシーボ効果とは
思い込みの力が、精神や身体に影響を与える現象のこと
プラシーボ効果(Placebo effect)は、医学・心理学分野でよく見られる現象で、実際には薬理学的な効果が無い治療(偽薬、疑似治療など)が、患者の信じる力や期待によって、症状の改善や治療効果があるかのように感じられる効果を指します。
この現象は、心の持つ力や心理的要因が、物理的な健康状態や感じる痛みにどの程度影響を及ぼすかを示しています。プラシーボ効果は、治療の一部として、また科学的な研究の中で新しい治療法の効果を評価する際のコントロールとして広く利用されています。
プラシーボ効果を引き起こすメカニズムは完全には解明されていませんが、一部は患者の期待や信念、さらには患者と医師との関係性によるところが大きいとされています。患者が治療に対して強く期待感を持つと、その期待が現実となるかのように体が反応することがあります。これは、心理的ストレスの軽減や心地よい感覚の増強、痛みの軽減など、様々な形で現れます。
しかし、プラシーボ効果はあくまで一時的なものであり、実際に病状を改善する能力は持ち合わせていません。したがって、プラシーボはあくまで治療の一部として考慮されるべきであり、実際の医療行為を代替するものではないことを理解することが重要です。
プラシーボ効果の由来
科学的研究によって、プラシーボ効果が初めて認められたのは、ハーバード・メディカル・スクールの麻酔学教授ヘンリー・ビーチャーが書いた論文『強力なプラシーボ(The Powerful Placebo)』がきっかけです。
彼が初めてプラシーボ効果を目にしたのは、1944年に米軍医として、南イタリアの沿岸地域に赴いた時のことでした。ドイツ軍のもう攻撃により、負傷兵が続出し、治療に使うモルヒネが不足するという事態に陥ってしまいました。
そこで、何人かの負傷兵にモルヒネの代わりに生理食塩水を注射したのですが。。。これが功を奏し、患者の痛みはすぐに和らぎ、そのおかげで致命的なショックを防ぐことができたのです。つまり、モルヒネだと勘違いして生理食塩水を飲んだにもかかわらず、思い込みの力で痛みを和らげることに成功したのです。
プラシーボ効果の具体例
ではここからはプラシーボ効果の日常的な事例をいくつか紹介していきます。
- ブランド製品の使用
- スポーツドリンクや」エネルギー補給食品
- カフェインフリーのコーヒー
事例1:ブランド製品の使用
ブランド製品は高品質という期待があります。ブランド製品を手に入れたとき、消費者はその期待に基づき、商品が実際以上に優れたものであると感じることがあります。たとえば、高価なブランドのバッグを手に入れた人は、そのバッグが一般的なバッグよりも堅牢で、長持ちすると信じることがあります。これはプラシーボ効果の一種で、ブランド名と価格が消費者の満足度や製品に対する期待を高めることがあります。
事例2:スポーツドリンクやエネルギー補給食品
運動時にスポーツドリンクやエネルギー補給食品を摂取すると、パフォーマンスが向上するという期待があります。その結果、運動能力が実際よりも向上したと感じることがあります。例えば、マラソンランナーがレース中にエネルギージェルを摂取したとき、その行為によって体力が回復すると感じ、その結果として実際のパフォーマンスが向上することがあります。
事例3:カフェインフリーのコーヒー
コーヒーを飲むことで覚醒するという期待があります。そのため、カフェインフリーのコーヒーを飲んだときでも、カフェインを含むコーヒーを飲んだときと同じような覚醒感を感じることがあります。例えば、朝のルーチンとしてカフェインフリーのコーヒーを飲む人は、コーヒーの香りと味、飲むという行為そのものから覚醒感を得て、一日を始めるエネルギーを感じることがあります。
プラシーボ効果の実験
ファブリツィオ・ベネデッティは、1990年代からプラシーボ効果の研究を始め、その結果、治療の約束が脳の特定の領域を活性化することを発見しました。これらの領域は、事象の重要性と脅威の深刻さを評価する役割を果たしています。
彼はまた、パーキンソン病患者に対するプラシーボの効果についても研究し、プラシーボを投与することで運動を制御するニューロンの発火率が約40%減少し、患者がより容易に動けるようになることを発見しました。
さらに詳細な実験を見てみると、彼は手を握る運動中に被験者にモルヒネを投与し、後に被験者に知らせずにモルヒネをプラシーボに置き換えるという実験も行いました。
この研究では、モルヒネを投与された後にプラシーボを受け取った被験者が、コントロールグループの患者よりもかなり痛みを耐えることができたと報告されています。
ノセボ効果とは
思い込みの力が、精神や身体に悪影響を与える現象のこと
ノセボ効果は、患者がネガティブな結果を予想すると、その予想が現実になるという現象を指します。この効果は、患者が副作用や病状の悪化を恐れることで、その恐怖が現実になるというものです。
ノセボ効果は、プラシーボ効果の反対の現象として知られています。プラシーボ効果は、偽の治療や薬が患者の期待や信念によって実際に症状の改善をもたらす現象を指します。しかし、ノセボ効果では、患者のネガティブな期待や恐怖が、症状の悪化や新たな症状の出現を引き起こすことがあります。
ノセボ効果は、医療の現場で非常に重要な考慮事項となっています。医療提供者は、患者の期待や恐怖が治療結果に影響を及ぼす可能性があることを理解し、それに対応するための戦略を持つことが求められます。これには、患者とのコミュニケーション、情報の提供、患者の不安の軽減などが含まれます。
ノセボ効果の具体例
ではここからは、ノセボ効果の日常的な事例をいくつか紹介します。
- 薬の副作用
- 食物アレルギー
- ストレスと健康
事例1:薬の副作用
薬のパッケージに記載されている副作用を読むと、その情報が患者の心に強く影響を及ぼすことがあります。例えば、薬が頭痛を引き起こす可能性があると書かれていると、患者は頭痛を予期し始めるかもしれません。この予期が強くなると、実際に頭痛が発生する可能性があります。これはノセボ効果の一例で、患者の思い込み(この場合は副作用の予期)が身体的な症状を引き起こすことを示しています。
事例2:食物アレルギー
ある人が特定の食品に対してアレルギー反応を持つと自己診断した場合、その人はその食品を食べると体調が悪くなると予期するかもしれません。その結果、その食品を食べた後に実際に体調不良を経験することがあります。しかし、医学的な検査ではアレルギー反応が確認できない場合もあります。これは、その人が自分がアレルギーを持っているという思い込みが、実際の身体的な症状(この場合は体調不良)を引き起こしている可能性があることを示しています。
事例3:ストレスと健康
ストレスが健康に悪影響を及ぼすと信じている人は、ストレスを感じると体調を崩しやすいです。これは、ストレスが健康に悪影響を及ぼすという思い込みが、実際に体調不良を引き起こすノセボ効果の一例です。この場合、ストレスを感じると体調が悪くなるという予期が、実際に体調不良を引き起こす可能性があります。
ノセボ効果の実験
あるイタリアの医師が、前立腺肥大の男性を対象とした実験を行いました。その際、まず患者を2つのグループに分けます。
そして、薬を投与されてから3ヶ月後のそれぞれの被験者の状態を観察しました。
実験の結果、②の患者の方が、副作用の報告が圧倒的に多かったのです。①の患者と比べると、3倍近い数だったことには驚きを隠せません。
倫理的には、薬の副作用を伝えるべきではありますが、だからと言ってそれを単に伝えれば良いということでもなさそうですよね。なぜなら、伝え方に配慮が無いと、患者に不要な苦しみを与えてしまう恐れもあるわけですから。
プラシーボ効果が発動する理由
ではここからは、プラシーボ効果が発動する理由を、ホルモンや神経伝達物質に着目して解説していこうと思います。
- エンドルフィン
- ドーパミン
- セロトニン
理由1:エンドルフィン
プラシーボ効果が痛みを軽減する一つのメカニズムは、脳が自然に産生する鎮痛物質であるエンドルフィンの放出に関与しています。プラシーボ(例えば、砂糖のピル)が痛みを和らげると信じると、脳はその期待に反応してエンドルフィンを放出します。エンドルフィンは、オピオイド受容体に結合し、痛みの感覚を減少させることで鎮痛効果を発揮します。
理由2:ドーパミン
プラシーボ効果はまた、報酬と快楽に関与する神経伝達物質であるドーパミンの放出にも関与しています。プラシーボが効果を発揮すると期待すると、脳はその期待に反応してドーパミンを放出します。ドーパミンは、快感を感じる能力を高め、全体的な気分を向上させることで、身体的な症状の改善を促進します。
理由3:セロトニン
プラシーボ効果は、気分と感情に大きな影響を与える神経伝達物質であるセロトニンのレベルにも影響を与えることが示されています。プラシーボが効果を発揮すると期待すると、脳はセロトニンの放出を増加させ、これが気分を向上させ、痛みを感じる閾値を上げることができます。
プラシーボ効果をマーケティングに活用する方法
ではここからは、プラシーボ効果をマーケティングに活用する方法をいくつか紹介します。
一つポイントをお伝えしておくと、消費者にどのような期待をさせ、どのようなポジティブな影響を与えるかが非常に大切になってきます。以上のことを踏まえて、マーケティングに活用する方法を見ていきましょう。
- 高級ブランディング
- 顧客体験の強調
- 社会的証明
方法1:高級ブランディング
方法2:顧客体験の強調
方法3:社会的証明
まとめ
プラシーボ効果とは|“思い込みの力”が我々に与える影響【事例を使って解説】
プラシーボ効果は、人間の思い込みの力が身体や精神に影響を与える心理現象で、実際には薬理学的な効果が無い治療が、患者の信じる力や期待によって、症状の改善や治療効果があるかのように感じられる効果を指します。
この効果は、エンドルフィン、ドーパミン、セロトニンといったホルモンや神経伝達物質の放出に関与しています。一方で、ノセボ効果はプラシーボ効果の反対で、患者がネガティブな結果を予想すると、その予想が現実になる現象を指します。
これらの効果はマーケティングにも活用され、高級ブランディング、顧客体験の強調、社会的証明などの方法で消費者の期待を操作し、製品やサービスの評価を高めることが可能です。
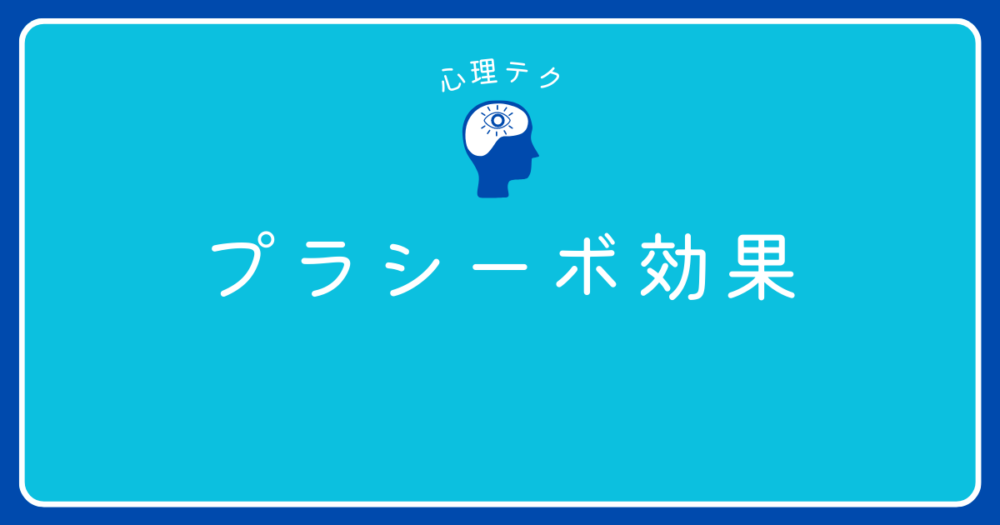
-1.jpg)

プラシーボ効果とは|“思い込みの力”が我々に与える影響【事例を使って解説】