ベンジャミンフランクリン効果とは、他者を助けることで、その人に好意を感じるという心理現象のことです。
あなたは、人に助けを求めているでしょうか。もし、求めていないのであれば、それは非常にもったいないことをしていると言えるでしょう。なぜなら、他者から好意を獲得すできる機会を逃しているからです。
実は、上記の定義にもあります通り、我々は人を助けることで、助けた対象に好意を寄せるというにわかに信じがたい心理傾向があります。
しかし、なぜそのような現象が起こるのでしょうか。そして、どのような心理構造から助けることによって好意を感じるのでしょうか。本記事では、その心理的メカニズムのみならず、それを営業やマーケティングに活用する方法などについても解説していきます。
というわけで本日は、
ベンジャミン・フランクリン効果とは|助けを求めて売上を爆上げする心理戦略
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
ベンジャミン・フランクリン効果とは
他者を助けることで、その人に好意を感じるという心理現象
ベンジャミン・フランクリン効果(Benjamin Franklin Effect)は、自分が他人に喜んで何かをしてあげることで、その人に対してより好意的な感情を抱くようになる現象を指します。この効果は、アメリカの発明家であり政治家でもあったベンジャミン・フランクリンにちなんで名付けられました。
フランクリンは、他人から借りたり、他人に頼むことが人間関係を深める力があると考えていました。彼は、自分が他人に恩恵を与えることで、その人との関係がより親密になると感じたことがありました。この考えは、後に心理学者によって研究され、フランクリン効果という名前で認識されるようになりました。
この効果は、認知的不協和理論と関連しています。認知的不協和とは、人間が持つ複数の認知(信念や態度、行動など)が一貫しない状態を指します。認知的不協和が生じると、人は自分の信念や態度を変えることで矛盾を解消しようとする傾向があります。
ベンジャミン・フランクリン効果の背後には、人が誰かに善意を示すと、その人に対して好意を持っていると自分自身に合理化することで、認知的不協和を解消しようとするというメカニズムが働いているとされています。そのため、他人に親切にすることで、自分自身がその人に対してより好意的な感情を持つようになるのです。
ベンジャミンフランクリン効果の具体例
では、ここからは、ベンジャミンフランクリン効果の事例をいくつか紹介しようと思います。
- 職場での協力
- 隣人との関係
- 学校での友達作り
事例1:職場での協力
ある同僚が困っている様子を見つけたとき、自分から積極的に協力やアドバイスを提供します。その結果、その同僚に対してより好意的な感情を持ち、お互いの信頼関係が深まる可能性があります。
事例2:隣人との関係
隣人が荷物を持ち上げるのに苦労しているのを見かけた場合、手伝いを申し出ることができます。その結果、隣人に対する好意が増し、良好な関係が築かれることがあります。
事例3:学校での友達作り
新しい学校やクラスで友達を作る際、他の生徒に勉強や宿題を手伝ったり、困っているときに助けを提供することで、自分自身がその生徒に対して好意的な感情を持ち、友達関係が築かれやすくなります。
なぜベンジャミンフランクリン効果が発動するのか
ベンジャミン・フランクリン効果が発動する理由は、認知的不協和の解消を目指す人間の心理的メカニズムによるものです。認知的不協和とは、人間が持つ複数の認知(信念や態度、行動など)が一貫しない状態を指します。認知的不協和が生じると、人は自分の信念や態度を変えることで矛盾を解消しようとする傾向があります。
例えば、あなたが特定の人に対して中立的な態度を持っていたとします。しかし、その人が助けを必要としている時に、あなたが自発的に手助けをすると、あなたの行動と中立的な態度が一貫しない状態が生じます。この認知的不協和を解消するため、あなたは自分の態度を変えることで、行動と信念を一致させようとします。つまり、あなたはその人に対して好意的な感情を持つようになります。
ベンジャミン・フランクリン効果は、認知的不協和の解消を通じて発動します。他人に善意を示す行動を取ることで、自分がその人に対して好意を持っていると自分自身に合理化し、認知的不協和を解消することができます。その結果、他人に親切にすることで、自分自身がその人に対してより好意的な感情を持つようになるのです。
ベンジャミンフランクリン効果の実験
ベンジャミン・フランクリン効果に関連する有名な実験のひとつは、1969年に心理学者ジェラルド・バーガー(Jecker and Landy)によって行われた研究です。この研究は、善意の行動が好意の感情を引き出すというベンジャミン・フランクリン効果を調査するために行われました。
実験の内容は以下の通りです。
実験参加者は、知能テストに参加するように指示されました。テスト終了後、参加者はテストの結果に基づいて、金銭的報酬を受け取りました。
参加者はその後、3つの異なる条件のいずれかに割り当てられました。
最後に、参加者は実験者に対する好意度を評価するアンケートに回答しました。
この実験の結果、実験者に直接頼まれて報酬を返した参加者(条件a)は、他の2つの条件の参加者よりも実験者に対して高い好意度を示しました。これはベンジャミン・フランクリン効果が働いていることを示しており、他人に善意を示す行為が、その人に対する好意的な感情を引き出すことを実証しています。
ベンジャミンフランクリン効果を営業に活用する方法
では、ここからはベンジャミンフランクリン効果を営業に活用する方法をいくつか紹介します。
- 顧客に頼みごとをする
- 顧客からアドバイスを求める
- 顧客と協力する機会を作る
方法1:顧客に頼みごとをする
ベンジャミン・フランクリン効果は、他人に頼みごとをすることで、その人に対する好意を引き出すことができるという点にあります。営業マンは、顧客に小さな頼みごとをすることで、顧客が営業マンに好意を抱くようになる可能性があります。
例えば、営業マンが顧客に、市場調査の一環としてアンケートに答えてもらうよう頼むことができます。顧客が頼みを引き受けることで、顧客は営業マンに対して好意的な感情を持つことが期待できます。
方法2:顧客からアドバイスを求める
営業マンが顧客からアドバイスや意見を求めることで、顧客は営業マンに対して好意を持つようになる可能性があります。
例えば、営業マンが新しい製品開発のアイデアについて顧客の意見を求めることができます。顧客が自分の意見やアドバイスを提供することで、営業マンに対して好意的な感情を抱くことが期待できます。
方法3:顧客と協力する機会を作る
営業マンが顧客と協力する機会を作ることで、顧客は営業マンに対して好意を持つようになる可能性があります。
例えば、営業マンが顧客と一緒に業界イベントやワークショップに参加し、共同でプロジェクトを進めることができます。顧客が営業マンと協力して何かを達成することで、顧客は営業マンに対して好意的な感情を持つことが期待できます。
ベンジャミンフランクリン効果を効果的に使うコツ
ここまでの内容で、人に助けを求めることの重要性については理解していただけたのではないでしょうか。しかし、実際に人に助けを求めることは、罪悪感などから言い出しづらいところもあるでしょう。というわけで、ここからはベンジャミンフランクリン効果をより効果的に活用する方法を紹介していきます。
結論から言えば、「能力を褒める+助けを求める」という方程式を使って助けを求めるようにしましょう。最初に相手の能力を褒めることにより、気持ちよく助けてくれるようになります。
たとえば、これはオータニが仕事で、ある企業の食品のショートムービーを撮影していた時の話です。具体的には、インスタグラムのリール投稿ですね。
オータニは、あまりカメラや動画の撮影経験がなかったため、美しくショートムービーを撮影するのに苦戦していました。そこで、撮影に同行していた無口なカメラマンに目を付け、オータニは彼に下記のようなお願いをしたのです。
「先ほどから〇〇さんの撮影を拝見していましたが、すごく綺麗ですね(褒め)。何かコツとかってあるんですか?」
すると、カメラマンは、オータニの要求を受け入れてくれました。さらに、調子に乗ったオータニは「もしよかったら、このムービーを一度撮影してみてくださいよ〜」なんてお願いもしたのですが、それも快くOKという結果となりました。
最終的には、カメラマンが「カメラっていうのは〜」なんて語り出しちゃうくらい気に入られてしまいましたね。笑
ベンジャミンフランクリン効果をマーケティングに活用する方法
では、ここからはベンジャミンフランクリン効果をマーケティングに活用する方法をいくつか紹介します。
- 顧客参加型キャンペーン
- ユーザーからのフィードバックを求める
- コミュニティへの参加・貢献
方法1:顧客参加型のキャンペーン
マーケティング活動において、顧客が参加できるキャンペーンを実施することで、顧客は企業やブランドに対して好意を持つようになる可能性があります。
例えば、SNS上で写真コンテストを開催し、顧客に自社製品を使った写真を投稿してもらうよう促すことができます。顧客が参加することで、顧客は企業やブランドに対して好意的な感情を持つことが期待できます。
方法2:ユーザーからのフィードバックを求める
企業が顧客からフィードバックや意見を求めることで、顧客は企業に対して好意を持つようになる可能性があります。
例えば、製品やサービスに関する顧客満足度調査を行い、顧客に自分たちの意見を提供してもらうことができます。顧客が自分の意見を聞いてもらえると感じることで、企業に対して好意的な感情を持つことが期待できます。
方法3:コミュニティへの参加・貢献
企業が顧客と同じコミュニティに参加し、そのコミュニティに貢献することで、顧客は企業に対して好意を持つようになる可能性があります。
例えば、企業が地元のイベントやチャリティ活動に積極的に参加し、顧客と同じ目的や価値観を共有することができます。顧客が企業がコミュニティに貢献していることを認識することで、企業に対して好意的な感情を持つことが期待できます。
まとめ
ベンジャミン・フランクリン効果とは|助けを求めて売上を爆上げする心理戦略
他者に助けを求めること、他者を助けること、が重要であることをしっかり理解してもらえたでしょうか。今まで、助けを求めることは悪だと感じていた方も多いでしょう。
しかし、助けを求めることは、相手から好意を獲得する最強の心理戦略になります。なので、ぜひあなたの営業・マーケティング戦略にベンジャミンフランクリン効果を導入するようにしていきましょう。
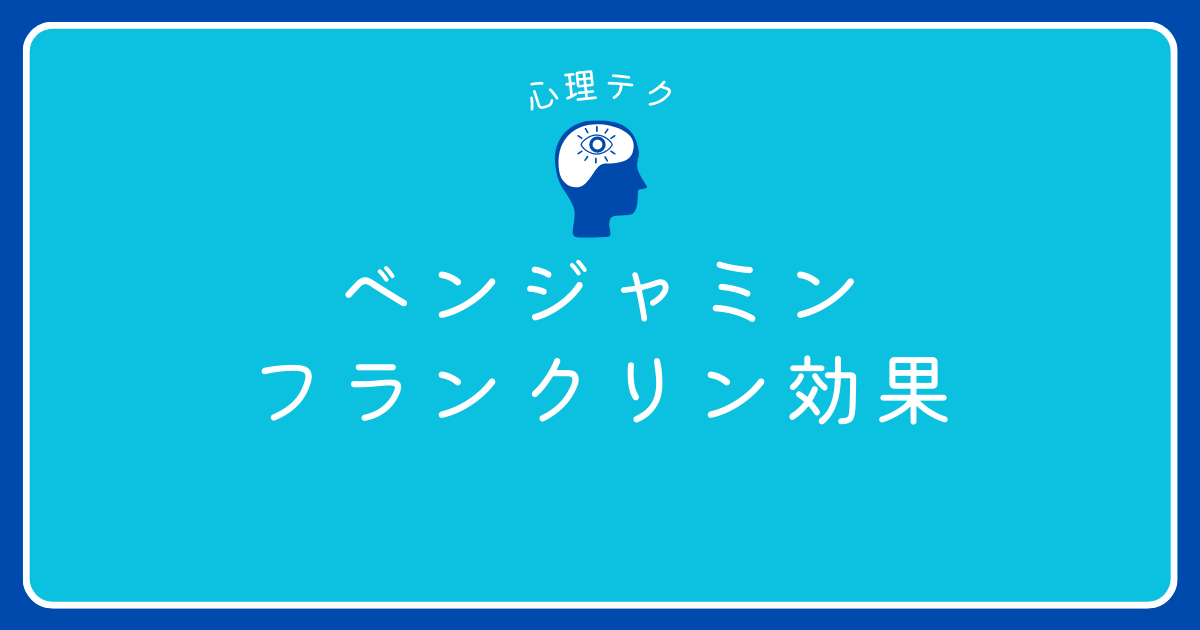
-1.jpg)

この効果を求めていた!