ローボールテクニックとは、最初に好条件の要求を承諾させ、後から好条件を引いたり、悪い条件を足したりする心理テクニックのことです。
たとえば、「50%セールス中!」という広告をみて洋服店に入ったものの、その対象は一部の商品のみで、「まぁせっかく来たし〜」ということで、商品を購入してしまったなんて経験はありませんか。
このように、我々は、最初に好条件の要求を呑んでしまうと、後に引けなくなってしまうのです。しかし、なぜこのような現象が起こるのでしょうか。本記事では、ローボールテクニックが発動する心理学的理由、またそれを営業やマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
ローボールテクニックとは
最初に好条件の要求を承諾させ、後から好条件を引いたり、悪い条件を足したりする心理テクニック
ローボールとは、「低い球」を意味するのですが、捕球しにくい「高い球」でも、先に捕球しやすい「低い球」を取らせることで、捕球しやすくなるというところから来ています。ローボールテクニックは、「特典除去法」「承諾先取り法」とも言われています。
このテクニックは、人々が一度何かに同意すると、その後で条件が変わったとしてもその決定を覆すのが難しくなるという心理的な傾向を利用しています。ローボールテクニックの一般的な手順は次のとおりです。
このテクニックは、販売や交渉の状況でしばしば使用されます。たとえば、販売員は最初に低価格を提示して製品の購入に同意させ、その後で追加のコスト(保証料、送料、取り付け料など)を追加することがあります。
ただし、このテクニックは、利用されると人々が騙されたと感じ、長期的な信頼関係を損なう可能性があるため、使用には注意が必要です。
ローボールテクニックの具体例
では、いくつか具体例をみていきましょう。
- 自動車ディーラー
- ケーブルテレビ会社
- ホームリノベーション
事例1:自動車ディーラー
ある人が新しい車を購入する際、ディーラーは非常に魅力的な価格を提示します。購入者がこの提案を受け入れ、購入を決定した後で、ディーラーは追加の費用(保証、メンテナンスパッケージ、税金など)を明らかにします。しかし、購入者は既に購入を決定しているので、新しい条件にも同意することが多いです。
事例2:ケーブルテレビ会社
ケーブルテレビ会社はしばしば初めの数ヶ月間は割引料金を提供し、顧客が契約に同意した後で通常の高い月額料金に変更することがあります。しかし、多くの顧客はすでにサービスに慣れてしまっており、また新たなプロバイダーを探すのが面倒であるため、高額な料金を払い続けることが多いです。
事例3:ホームリノベーション
ホームリノベーションの業者は、最初に低い見積もりを提示して顧客を引きつけ、契約が結ばれた後で「予期せぬ問題」や「追加の必要な作業」を理由に費用を増やすことがあります。しかし、既にプロジェクトが始まっているため、顧客は新たなコストを受け入れざるを得ないことが多いです。
ローボールテクニックの実験
社会心理学者のロバート・チャルディーニ氏は、オハイオ州立大学で、心理学入門講座を受講している学生に、”嫌な活動への参加を取り付ける”といった実験を行います。
※嫌な活動=朝7時から始まる「思考過程に関する」研究に加わる
まず、被験者を2つのグループに分けます。
そして、それぞれの被験者の承諾率を調べました。
実験の結果、下記のような結果となったのです。
なんと、①と比べると、ローボールテクニックを使った内容(②)では、承諾率に2倍以上の大差を付けたのです。
さらに驚くべきことに、ローボールテクニックによって参加表明した学生の95%が、約束通り朝7時に実験に参加したのでした。
つまり、ただ目先の承諾を取り付けることに成功しただけではなく、実際にこちらの目的を達成することができたということですね。
ローボールテクニックは効果的な理由
以降では、なぜローボールテクニックが発動するのかについて解説します。
結論から言えば、コミットメントと一貫性の原理が発動するからです。
言動と一致した思考・行動を取りやすくなるという心理傾向
つまり、最初に相手からの要求に承諾してしまうことで、その後、好条件を引いたり、ちょっとした悪条件を足したとしても、それを貫こうとしてしまうわけです。
ローボールテクニックとフット・インザ・ドア
ここでは、ローボールテクニックと非常に勘違いされやすいフットインザドアについて解説していきます。
フット・インザ・ドアとは
フットインザドアとは、小さな承諾を積み重ねることで、本命の要求を承諾させやすくするテクニックのことです。
たとえば、男性に高価な貢物をさせたいのであれば、最初はあえて小さな貢物からさせましょう。最初に、食事代を出させ、映画代を出させ、ディナーを奢らせ…という形で最終的にバッグをねだると、バッグからねだるよりも、高確率で購入してもらえるようになります。
このように、最初は小さかった貢物も、小さな要求をコツコツ通すことによって「大きな貢物」へと変化していくのです。
ローボールテクニックとの違い
ローボールテクニックとフット・インザ・ドアの決定的な違いは、条件の「足し算・引き算」がないところですね。
フット・インザ・ドアは、最終的に承諾してもらいたい要求に向かって、コツコツと小さな承諾をもらうというテクニックですが、
ローボールテクニックでは、最初に好条件の承諾させた後に、悪条件を足したり、好条件を引いたりします。
なので、お互い前述した「コミットメントと一貫性の原理」を利用しているところは同じですが、似て非なるテクニックと言えるでしょう。
営業で活用する3ステップ
ここからはローボールテクニックを営業に活用する時に意識する3ステップをお伝えしていきます。
初期の取引価格を低く設定する
追加価値を明示する
同意の維持を促す
ステップ1:初期の取引価格を低く設定する
まず、商品やサービスの価格を相手が納得できる範囲に設定します。これにより、顧客は購入に対して前向きになりやすくなります。
ステップ2:追加価値を明示する
顧客が購入に同意した後、追加の価値(例えば、拡張保証、追加サービスなど)を提案します。これらの追加価値は当初の取引価格には含まれていないことを明確にし、その追加価値に対して追加の費用が発生することを説明します。
ステップ3:同意の維持を促す
顧客が既に購入に同意しているため、追加の費用や条件に対しても同意しやすくなります。しかし、顧客が新たな条件に同意するかどうか確認するために、再度確認することが重要です。
これらの手法を使用する際は、常に公正かつ誠実に行動することが重要です。ローボールテクニックは、誤解や不信を引き起こす可能性があるため、顧客との長期的な関係を築くためには、透明性と信頼性が不可欠です。
マーケティングでの活用事例
では、ローボールテクニックを実際にマーケティングに活用した事例を3つほど見ていきましょう。
- サブスクリプションボックスサービス
- スマートフォンアプリ
- オンラインコース
事例1:サブスクリプションサービス
あるサブスクリプションサービスは、新規顧客に初回限定の割引価格や無料トライアルを提供します。顧客は割引価格で商品を試すことで、サービスの価値を実感し、その後定期的な料金が適用される通常プランに移行する可能性が高まります。
事例2:スマートフォンアプリ
スマートフォンアプリ開発者は、アプリの無料版を提供して顧客にダウンロードさせます。顧客が無料版のアプリに満足し、その後有料版にアップグレードすることで、開発者は収益を上げることができます。有料版では広告が表示されない、追加機能が利用できるなどのメリットを強調することで、顧客にアップグレードを促します。
事例3:オンラインコース
オンライン教育プラットフォームでは、無料のトライアル期間や一部のコンテンツへのアクセスを提供することで、顧客にサービスの価値を実感させます。その後、顧客は全体のコンテンツにアクセスできる有料プランに移行することを検討しやすくなります。
まとめ
ローボールテクニックとは|悪用厳禁の説得術
ローボールテクニックは、様々な会社で活用されている最強の心理テクニックです。もし、まだ自身の営業戦略に導入していないのであれば、何度もこの記事を繰り返し読み、実践するようにしましょう。
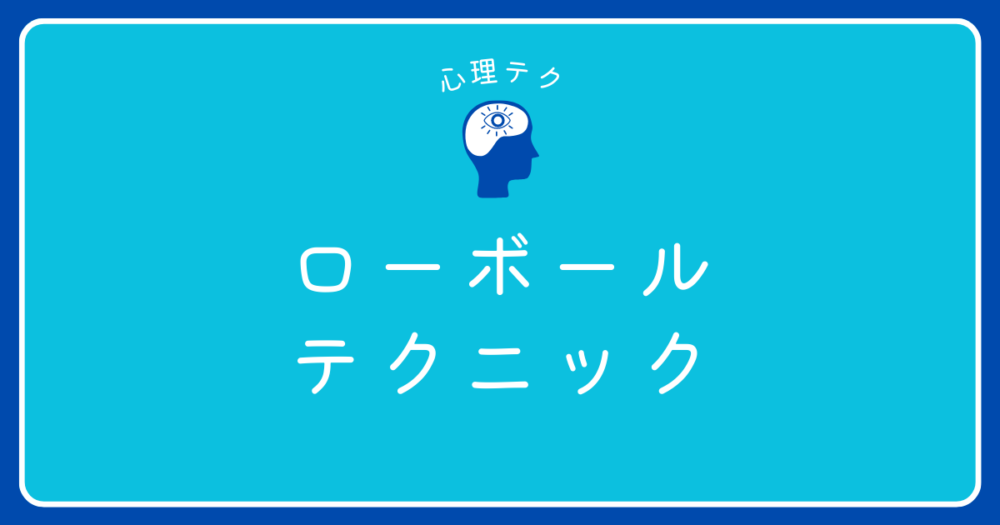
-1.jpg)

ローボールテクニックとは|悪用厳禁の説得術