グランファルーン・テクニックとは、意味のない共通点に基づいてグループに分け、そのグループのアイデンティティや連帯感を高める方法のことです。
たとえば、運動会では、赤組と白組に別れてお互い競い合いますが、赤組・白組という適当に振り分けられた特別意味のない共通点であるにもかかわらず、それぞれの組織で連帯感が生まれたりします。このように、我々は、特別な共通点を持っていなかったとしても、同じ組に割り振られただけで好意を感じてしまったりするのです。
しかし、なぜこのような現象が起こるのでしょうか。本記事では、グランファルーンテクニックが発動する心理学的理由、またそれを営業やマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
グランファルーン・テクニックとは
意味のない共通点に基づいてグループに分け、そのグループのアイデンティティや連帯感を高める方法
グランファルーン・テクニックは、人々を意味のない共通点に基づいてグループに分け、そのグループのアイデンティティや連帯感を高める方法です。この言葉は、アメリカの作家カート・ヴォネガットが1963年に発表した小説『猫のゆりかご』で初めて登場しました。彼はグランファルーンを「無意味な結束を持つ人々の集団」と定義しました。
グランファルーン・テクニックは、マーケティング、広告、政治などの分野でよく使われます。人々がある特定のグループに属すると感じることで、そのグループの一員としてのアイデンティティや連帯感を高め、特定の目的や目標を達成することが狙いです。例えば、同じスポーツチームのファン、同じ出身地の人々、同じ誕生月の人々など、本質的には関係のない共通点を持つグループが対象となることが多いです。
しかし、グランファルーン・テクニックは、人々を分断し、偏見や差別を助長する可能性もあるため、批判されることもあります。それにもかかわらず、このテクニックは様々なコンテクストで効果的に機能することが示されており、人々がグループに属することに価値を見出す心理的な傾向を利用しています。
グランファルーンテクニックとヒトラーの大衆煽動術
ヒトラーは、ナチス党を率いてドイツ国民に対して大衆煽動を行いました。彼は、強力な演説と巧みなプロパガンダを通じて、多くのドイツ人に共感を呼びかけることに成功しました。この過程で、ヒトラーはグランファルーン・テクニックの要素を利用して、ドイツ国民に一体感を持たせ、彼らを支持させました。
共通のアイデンティティを作る
共通の敵を作る
手段行動を促す
ステップ1:共通のアイデンティティを作る
ヒトラーは、「アーリア人」という理想的なドイツ人のイメージを作り出し、ドイツ国民にそのアイデンティティを共有させました。彼は、アーリア人を優れた民族として讃え、ドイツ人の民族意識を高めました。これにより、多くのドイツ人が自分たちが特別な一員であると感じるようになりました。
ステップ2:共通の敵を作る
ヒトラーは、ドイツの経済危機や第一次世界大戦の敗北に対する責任を、ユダヤ人や共産主義者などの特定のグループに押し付けました。彼は、これらのグループを共通の敵として訴え、ドイツ国民の敵意を煽りました。これにより、多くのドイツ人が自分たちの苦境から脱するために、これらの敵と戦わなければならないと感じました。
ステップ3:集団行動を促す
ヒトラーは、大規模な集会やパレードなどのイベントを開催し、ドイツ国民を一つにまとめました。これらのイベントでは、国家やナチス党のシンボルが使われ、国民に一体感を持たせました。また、ヒトラー自身が熱狂的な演説を行い、国民の感情を共鳴させました。
グランファルーン・テクニックの具体例
では、いくつか具体例をみていきましょう。
- スポーツチームのファン
- 同じ誕生日の人々
- 出身地に基づく約束
事例1:スポーツチームのファン
スポーツチームのファンは、同じチームを応援することで強い絆や連帯感を持ちます。この共通の興味が、ファン同士の友情や忠誠心を生み出すことがあります。実際には、ファンたちの個人的な特徴や価値観が異なる場合でも、同じチームを応援することで一体感が生まれます。
事例2:同じ誕生月の人々
同じ誕生月の人々は、特に関連性のない共通点を持っていますが、それによって結束感を感じることがあります。例えば、誕生月が同じ人々同士でパーティーを開いたり、SNSで共有したりすることで、一種の連帯感を得ることができます。
事例3:出身地に基づく結束
出身地によってグループを作ることも、グランファルーン・テクニックの一例です。同じ地域出身の人々は、地域の文化や習慣、方言などを共有していることから、親近感や連帯感を感じることがあります。実際には、出身地以外の個人的な価値観や興味が異なる場合でも、出身地を共有することで一体感が生まれることがあります。
グランファルーン・テクニックはなぜ発動するのか
グランファルーン・テクニックが機能する心理学的および脳科学的理由は、主に人間の社会的な欲求や所属感の重要性に関連しています。以下に、それらの要因をわかりやすく説明します。
- 所属感の欲求
- 類似性に基づく親近感
- 自己類型化
理由1:所属感の欲求
人間は社会的な生き物であり、所属感や結束感を持つことで安心感や自己肯定感が得られます。グループに所属することで、人々は自分のアイデンティティを確立し、自己の価値を高めることができます。グランファルーン・テクニックは、この所属感の欲求を利用して、表面的な共通点を持つ人々を結びつけます。
理由2:類似性に基づく親近感
人間は、自分に似た特徴や興味を持つ他者に親近感を感じる傾向があります。類似性は信頼感や安心感を生み出し、コミュニケーションや協力を促進します。グランファルーン・テクニックは、意味のない共通点を持つ人々をグループ化することで、この類似性に基づく親近感を引き出します。
理由3:自己類型化
人間は、自分自身をある程度のカテゴリーに分類することで、自己認識を簡素化し、状況に応じた適切な行動をとりやすくします。このプロセスでは、自分が属するグループ(内集団)と他のグループ(外集団)を区別し、内集団の一員として行動することが求められます。グランファルーン・テクニックは、この自己類型化のプロセスを利用して、人々があるグループに所属することに価値を見出させます。
グランファルーン・テクニックの実験
グランファルーン・テクニックに関連する実験の中で有名なものに、ミニマル・グループ・パラダイム(最小グループ効果)があります。
この実験は、1970年代にイギリスの社会心理学者ヘンリー・タジフェルによって初めて行われました。ミニマル・グループ・パラダイムは、グループ間の差別と偏見がどのように発生するかを調べるための実験です。
この実験は、グランファルーン・テクニックの原理を実証しており、人々がどれほど簡単に無意味な共通点に基づいてグループに分けられ、そのグループに対して忠誠心や連帯感を持ち始めるかを示しています。また、この実験は、偏見や差別がどのようにして生まれるかに関する重要な洞察を提供しています。
グランファルーン・テクニックを営業に活用する方法
ではここからは、グランファルーンテクニックを営業に活用する方法を紹介します。
- 共通の趣味や興味を見つける
- 学歴や出身校を活用する
- SNS上の共通のコミュニティーやグループを利用する
方法1:共通の趣味や興味を見つける
営業パーソンは、顧客との会話の中で共通の趣味や興味を見つけ、それを利用して親近感を築くことができます。例えば、顧客がスポーツチームのファンであることがわかった場合、営業パーソンもそのチームの話題を取り入れ、共感を示すことで、信頼関係を構築します。これにより、顧客は営業パーソンをより信頼し、商品やサービスに対しても興味を持ちやすくなります。
方法2:学歴や出身校を活用する
営業パーソンは、顧客と同じ学歴や出身校に関連する話題を取り上げることで、一体感を生み出すことができます。例えば、顧客が特定の大学の卒業生であることがわかった場合、営業パーソンはその大学の話題や思い出を共有し、顧客との共通点を強調します。これにより、顧客は営業担当者との親近感を感じ、よりオープンなコミュニケーションが可能になります。
方法3:SNS上の共通のコミュニティやグループを利用する
営業パーソンは、顧客と共通のSNS上のコミュニティやグループに関連する話題を取り上げることで、一体感を生み出すことができます。例えば、顧客が特定のオンラインコミュニティに参加していることがわかった場合、営業パーソンはそのコミュニティでの話題や経験を共有し、顧客との共通点を強調します。これにより、顧客は営業パーソンとの親近感を感じ、よりオープンなコミュニケーションが可能になります。
グランファルーン・テクニックをマーケティングに活用する方法
ではここからは、グランファルーンテクニックをマーケティングに活用する方法を紹介します。
- ターゲット市場に合わせたコピーを書く
- 共通の敵を作る
- Weメッセージを使う
方法1:ターゲット市場に合わせたコピーを書く
マーケティングにおいて、ターゲット市場のニーズや関心に合わせたコピーを作成することで、顧客との一体感を生み出し、ブランドへの支持を高めることができます。顧客は自分たちのアイデンティティや価値観が反映されたコピーを通じて、ブランドや商品に対する親近感を持ち、購買意欲を高めるでしょう。
たとえば、20代の女性をターゲットにした化粧品ブランドは、彼女たちのライフスタイルや価値観に合わせたキャッチフレーズやコピーを作成することができます。例えば、「自分らしさを大切にするあなたへ」や「あなたの個性を引き出すメイクアップ」といったコピーを用いることで、ターゲット市場の女性たちが自分たちの価値観やアイデンティティに共感し、ブランドに対する興味や購買意欲を高めるでしょう。
方法2:共通の敵を作る
マーケティングにおいて、共通の敵を作ることで、顧客との一体感を生み出し、ブランドへの支持を高めることができます。
たとえば、環境に配慮した製品を提供する企業は、環境破壊や資源の浪費といった共通の敵を設定し、顧客とともに環境問題への取り組みを強調することができます。この戦術により、顧客はその企業の製品やサービスを選ぶことで、自分たちも環境保護の一員であると感じ、購買意欲を高めるでしょう。
方法3:Weメッセージを使う
Weメッセージを使って、顧客と一緒になって目標を達成することを強調することで、顧客との一体感を生み出し、ブランドへの支持を高めることができます。
たとえば、あるフィットネスアプリが、「一緒に健康的なライフスタイルを手に入れましょう」といったWeメッセージを用いて、マーケティング活動を展開することができます。このアプローチにより、顧客はそのアプリを使用することで、自分たちも健康的なライフスタイルを追求する仲間の一員であると感じ、アプリの利用意欲を高めるでしょう。
まとめ
グランファルーン・テクニックとは|大衆扇動に使われる恐怖の心理学
グランファルーンテクニックは、大衆煽動でも使われる、一歩間違えると犯罪までにも発展するような心理テクニックです。
しかし、この記事を読んでいるあなたは顧客の悩みを解決することを目的とした立派な営業マン、マーケターであることを信じております。
なので、ぜひあなたの販売戦略の中に、効果的にグランファルーンテクニックを入れるようにしていきましょう。
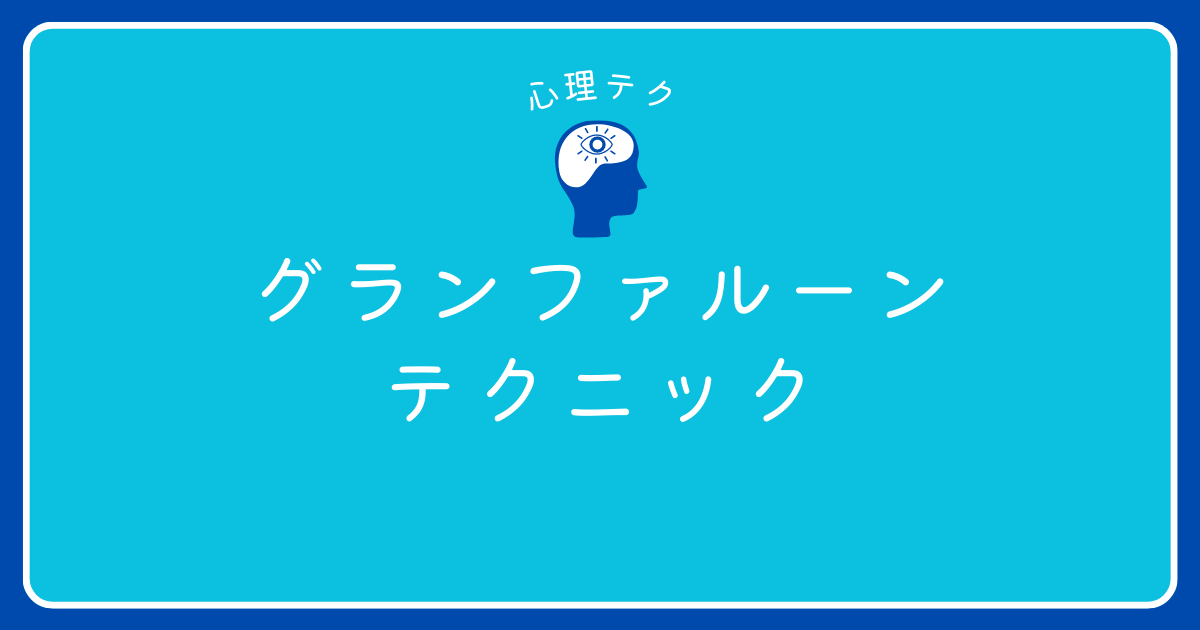
-1.jpg)

グランファルーン・テクニックとは|大衆扇動に使われる恐怖の心理学