フレーミング効果とは、同じ主張でも表現を変えることで、違う印象を受けてしまうという心理傾向のことです。
たとえば、「嫌い!」と言われるよりも、「好きではない」と言われた方が、なぜか軽い印象がありませんか。他にも、「死亡率10%の手術」と言われるよりも、「成功率90%の手術」と言われた方が手術を受ける気になりますよね。
このように、同じ主張でも表現が変われば、全く違う印象を受けることが分かります。本記事では、フレーミング効果を営業やマーケティングに活用する方法を紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
フレーミング効果とは
同じ主張でも表現を変えることで、違う印象を受けてしまうという心理傾向
フレーミング効果(Framing effect)は、情報の提示方法や文脈によって、人々の意思決定や選択が変化する心理学的な現象です。この効果は、情報がポジティブな枠組み(ゲイン・フレーム)で提示されると、リスク回避的な行動が促されることを示し、一方で、同じ情報がネガティブな枠組み(ロス・フレーム)で提示されると、リスクを取る行動が促されることを示します。
フレーミング効果は、1981年に心理学者ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴァルスキーによって初めて提唱されました。彼らの研究では、人々は損失や不利益を避けるためにリスクを取る傾向があることが示されました。フレーミング効果は、経済学、心理学、政治学、マーケティング、医療など、さまざまな分野で研究されています。
フレーミング効果を理解することは、意思決定におけるバイアスや認知の歪みに対処し、より効果的なコミュニケーションやマーケティング戦略を立てる上で重要です。また、個人や組織がフレーミング効果に影響されず、客観的かつ合理的な意思決定を行うための対策を講じることも重要です。
フレーミング効果の具体例
では、いくつか具体例をみていきましょう。
- セールスやマーケティング
- 政治
- 仕事や学業
事例1:セールスやマーケティング
店舗やオンラインショップでは、商品を売り込むためにフレーミング効果が利用されます。例えば、「70%オフ」ではなく、「原価の30%で購入可能」と表示されると、消費者はより魅力的に感じる傾向があります。また、「限定数量」や「期間限定」などの表現も、消費者に対して買い物を急がせる効果があります。
事例2:政治
政治家やメディアは、フレーミング効果を利用して政策やイベントを特定の視点から提示し、人々の意見や感情を誘導することがあります。例えば、移民政策に関して、「難民を救済する」というフレームでは支持者が増える一方、「国の負担が増す」というフレームでは反対者が増える傾向があります。
事例3:仕事や学業
職場や学校での評価やフィードバックでも、フレーミング効果が影響を及ぼすことがあります。例えば、同じフィードバックでも、「良い点が多いが改善すべき点もある」というフレームでは受け手は前向きに捉えることができますが、「悪い点があるが良い点もある」というフレームでは受け手は否定的に捉える傾向があります。
フレーミング効果の実験
フレーミング効果の有名な実験として、ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルツキーによって行われた「アジアの病」の実験が挙げられます。この実験は、1981年に発表され、フレーミング効果の概念を確立しました。実験の内容を分かりやすく説明します。
実験では、被験者に次のような2つのシナリオが提示されました。
シナリオ1(肯定的フレーム)
ある国でアジアの病が発生し、600人が命を落とす可能性があるとします。2つの対策プログラムがあります。
- プログラムA:200人が確実に助かります。
- プログラムB:1/3の確率で600人全員が助かり、2/3の確率で誰も助からない。
シナリオ2(否定的フレーム)
同じ状況で、以下の2つの対策プログラムがあります。
- プログラムC:400人が確実に死亡します。
- プログラムD:1/3の確率で誰も死亡せず、2/3の確率で600人全員が死亡します。
実際には、プログラムAとC、プログラムBとDは同じ結果をもたらすものです。しかし、被験者の選択はフレーミングによって大きく変わりました。
シナリオ1(肯定的フレーム)では、72%の被験者がプログラムA(200人が確実に助かる)を選び、リスク回避的な行動を取りました。一方、シナリオ2(否定的フレーム)では、78%の被験者がプログラムD(1/3の確率で誰も死なない)を選び、リスクを取る行動を取りました。
この実験は、同じ情報が肯定的なフレーム(ゲイン・フレーム)と否定的なフレーム(ロス・フレーム)で提示されると、人々の選択や意思決定が大きく変わることを示しています。フレーミング効果は、人間の意思決定におけるバイアスや認知の歪みを理解する上で非常に重要な概念となっています。
なぜフレーミング効果が発動するのか
フレーミング効果が発動する理由は、人間の心理的プロセスや脳機能に関連しています。ここでは、初心者にも分かるように、心理学的視点から説明します。
- 損失回避バイアス
- 認知のヒューリスティック
損失回避バイアス
人間は、損失を避けることに対して利益を得ることよりも強い動機を持っています。これは、損失が利益に比べて約2倍の強い感情的影響を持つためです。フレーミング効果では、情報が損失や不利益を強調することで、リスクを取る行動が促されます。
認知のヒューリスティック
人間は情報処理を効率化するために、簡略化されたルールやショートカットを使用します。フレーミング効果では、情報が簡単に評価できる形で提示されることで、意思決定が影響されます。
フレーミング効果を営業・マーケティングに活用する方法
- 感情フレーミング
- 損失フレーミング
- 限定フレーミング
方法1:感情フレーミング
言葉遣いに気を配ることは非常に大切なことです。なぜなら、ネガティブな表現を用いることで、他者からネガティブな評価をされてしまい、それが不買につながってしまうからです。たとえば、営業マンが、下記のような言葉を使っていたら、あなたはどう感じるでしょうか。
きっと、ポジティブなイメージを持つ人は少ないのではないでしょうか。
では、「嫌い」などのネガティブなメッセージを伝えたい場合は、どのように表現すれば良いのでしょうか。結論から言うと、「ポジティブな言葉+否定」という方程式を使うようにしましょう。たとえば、上記のネガティブワードを使って説明すると次のようになります。
このように表現するだけで、あなたへの印象が180度変わること間違いなしです。
方法2:損失フレーミング効果
利得の表現を損失の表現に変えるだけで、購買行動を一気に掻き立てることができます。なぜなら、前述した損失回避の法則が働くからです。
たとえば、電気の節約を提案するのであれば、下記のように表現を変えていきます。
他にも、化粧品を購入してもらいたいのであれば、下記のように表現を変えます。
このように、「利得」を「損失」にフレーミングするだけで、「すぐにでも購入しないと!」という焦燥感を引き出し、即決の購入へ導きやすくなります。
方法3:限定フレーミング
商品に限定性を設けることで、顧客の購買行動を刺激することができるようになります。なぜなら、我々は、限定された対象の価値を高く見積もる傾向があるからです(希少性の原理)。ただし、限定性を出すときには、少しフレーミング効果の力を借りる必要があります。具体的には下記のようなイメージです。
どうですか。同じ表現ではありますが、後者の方が「早く手に入れないと!」と感じますよね。
まとめ
フレーミング効果とは|営業やマーケティングで使える例を紹介
表現を変えるだけで、相手に与える影響が大きく変化するということを理解してもらえたでしょうか。
今まで、無意識に営業、マーケティング活動をしてきたかもしれませんが、これからは表現に気をつけて、前述した活動を行っていきましょう。
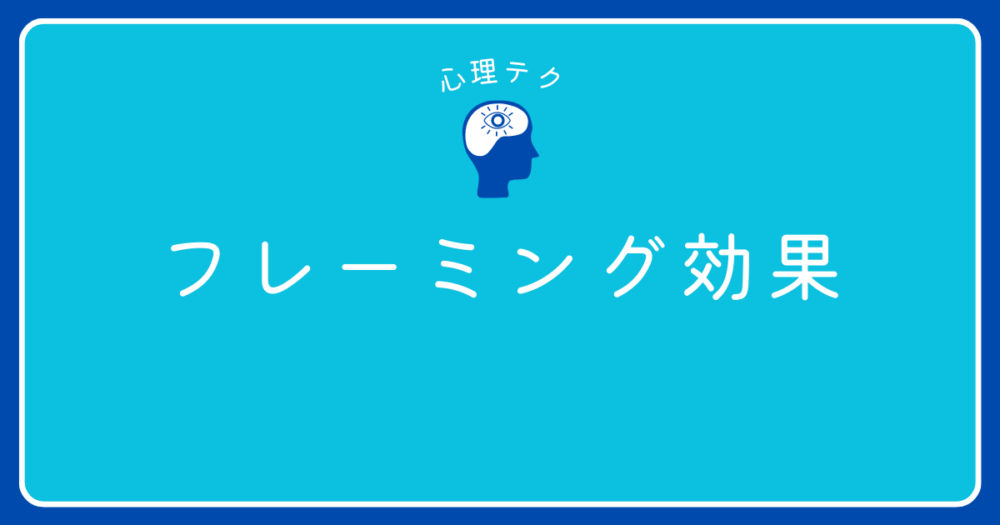
-1.jpg)

フレーミング効果とは|営業やマーケティングで使える例を紹介