利用可能性ヒューリスティックとは、「想起しやすさ」によって、認知が歪められてしまう現象のことです。
いきなり質問ですが、日本で多いのは下記のどちらでしょうか。
きっと多くの人は、自信満々に「コンビニに決まってるじゃん!」と答えてくれたと思うのですが、それは不正解です。実は、「美容院の数」の数の方が圧倒的に多いんですよね。この勘違いをさせているのが、利用可能性ヒューリスティックなのです。
しかし、なぜこのような現象が起こるのでしょうか。本記事では、利用可能性ヒューリスティックの心理的メカニズム、またそれをマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
利用可能性ヒューリスティックとは
「想起しやすさ」によって、認知が歪められてしまう現象
利用可能性ヒューリスティック(availability heuristic)は、人々が判断や意思決定を行う際に、情報の利用可能性や思い出しやすさに基づいて確率や頻度を推定する心理的なショートカットです。この概念は、1970年代にエイモス・トヴェルツキーとダニエル・カーネマンによって提案されました。
利用可能性ヒューリスティックは、人々が個人的な経験やメディアで目にする情報をもとに、現象や事象の発生確率を評価する際に役立ちます。しかし、このヒューリスティックは必ずしも正確な結果を導き出すわけではなく、認知バイアス(systematic errors in judgment and decision-making)を引き起こす可能性があります。
利用可能性ヒューリスティックの具体例
では、いくつか具体例をみていきましょう。
- 飛行機の恐怖
- 宝くじの購入
- クレーム対応
事例1:飛行機の恐怖
航空事故の報道が大々的に行われると、飛行機が非常に危険な交通手段であると感じる人が増えます。しかし、実際には飛行機は他の交通手段(自動車など)に比べて安全性が高いとされています。利用可能性ヒューリスティックの働きにより、メディアで目にする航空事故の報道が鮮明であるため、飛行機に対する恐怖が誘発されることがあります。
事例2:宝くじの購入
宝くじに当選した人の話がニュースやSNSで取り上げられることがあります。これにより、人々は自分も当選できる可能性が高いと感じることがあります。しかし、実際には宝くじの当選確率は非常に低いです。利用可能性ヒューリスティックが働くことで、当選者の話が鮮明に思い出され、誤って当選確率が高いと判断してしまうことがあります。
事例3:クレーム対応
ある商品やサービスに対して、クレームが多く寄せられることがあります。顧客からのクレームが目立つため、企業はその商品やサービスが広く不評であると判断し、大幅な変更を行うことがあります。しかし、実際にはクレームを出さない満足している顧客も多く存在することがあります。利用可能性ヒューリスティックにより、目立つクレーム情報が鮮明に思い出されることで、誤って商品やサービスの評価を下げてしまうことがあります。
利用可能性ヒューリスティックの実験
利用可能性ヒューリスティックを研究した有名な実験の一つは、アモス・トヴェルスキーとダニエル・カーネマンによって1973年に行われた「リスト生成実験」です。
実験では、被験者にアルファベットで始まる単語を順番にリストアップするタスクが与えられました。一部の被験者には、単語が子音で始まる場合のリストを作成するよう指示され、他の被験者には単語が母音で始まる場合のリストを作成するよう指示されました。
実験の結果、被験者は子音で始まる単語のリストを作成するのが難しいと感じたため、母音で始まる単語が一般的に多いと判断しました。しかし、実際には子音で始まる単語の方が多いです。この結果は、利用可能性ヒューリスティックが人々の判断に影響を与えることを示しています。つまり、被験者は自分が思いつきやすい単語をもとに、単語の出現頻度を評価しました。
この実験は、利用可能性ヒューリスティックが人々の判断や意思決定にどのように影響を与えるかを示す典型的な例です。思い出しやすい情報が判断の基準となり、実際の確率や頻度とは異なる結果を導くことがあります。
利用可能性ヒューリスティックが発動する理由
利用可能性ヒューリスティックが発動する理由は、人間の認知と情報処理の限界、および脳が効率的に機能するためのショートカットを取る傾向に関連しています。以下に、心理学的側面からの説明をいくつか示します。
- 認知の省エネ化
- 情報方の対処
- 経験の重要性
理由1:認知の省エネルギー化
人間の脳は、情報処理を効率的に行うために、省エネルギー化のためのショートカットを取ることがあります。利用可能性ヒューリスティックは、そのようなショートカットの一つであり、思い出しやすい情報に基づいて判断を行うことで、脳が迅速に結論に達することができます。
理由2:情報過多の対処
現代社会では、人々は情報過多にさらされています。脳は限られた容量で情報を処理するため、情報の取捨選択が必要になります。利用可能性ヒューリスティックは、情報の取捨選択を行いやすくするためのショートカットであり、鮮明で印象的な情報に基づいて判断を行うことができます。
理由3:経験の重要性
人々は、過去の経験から学び、それに基づいて未来の出来事に対処する能力を持っています。利用可能性ヒューリスティックは、個人の経験や観察に基づいて判断を行うことで、過去の経験が現在の状況にどのように適用されるかを評価する際のショートカットとなります。
利用可能性ヒューリスティックをマーケティングに活用する方法
では、ここからは利用可能性ヒューリスティックをマーケティングに活用する方法を紹介していきます。
- 単純接触効果を利用した広告展開
- キャッチーなイメージ戦略
- 口コミやインフルエンサーマーケティングの活用
事例1:単純接触効果を利用した広告展開
消費者に製品やブランドのメッセージを繰り返し伝えることで、記憶に定着させる効果があります。テレビCMやインターネット広告、SNSなどで同じメッセージやビジュアルを何度も表示することで、消費者は製品やブランドを思い出しやすくなり、購入を検討するきっかけになります。
事例2:キャッチーなイメージ戦略
顧客に強いイメージを植え付けることで、想起されやすくなります。たとえば、RIZAPのCMはとてもキャッチーですよね。普通に活しているだけで、頭の中にCMで使用されるBGMが流れたりします。他にも、レッドブルのCMなどもキャッチーですね。「翼を授ける」ということをコンセプトにした様々なCMがありますが、どれもユーモア溢れるものばかりです。
事例3:口コミやインフルエンサーマーケティングの活用
消費者が信頼する人物やインフルエンサーが製品やサービスを推奨することで、消費者の意識に製品やブランドが想起しやすくなります。例えば、インフルエンサーがSNSで製品を紹介したり、レビューや体験談を共有することで、その情報が消費者の記憶に定着しやすくなり、購入につながる可能性が高まります。
まとめ
利用可能性ヒューリスティックとは|意味・具体例・活用法を解説
利用可能性ヒューリスティックはかなり難しい概念ですよね。というのも、普段意識しないような内容ですから。
しかし、利用可能性ヒューリスティックを意識するだけで、あなたの販売活動を促進させることは間違いありません。
なので、ぜひ利用可能性ヒューリスティックをしっかり理解して、あなたの販売戦略に活かしてもらえればと思います。
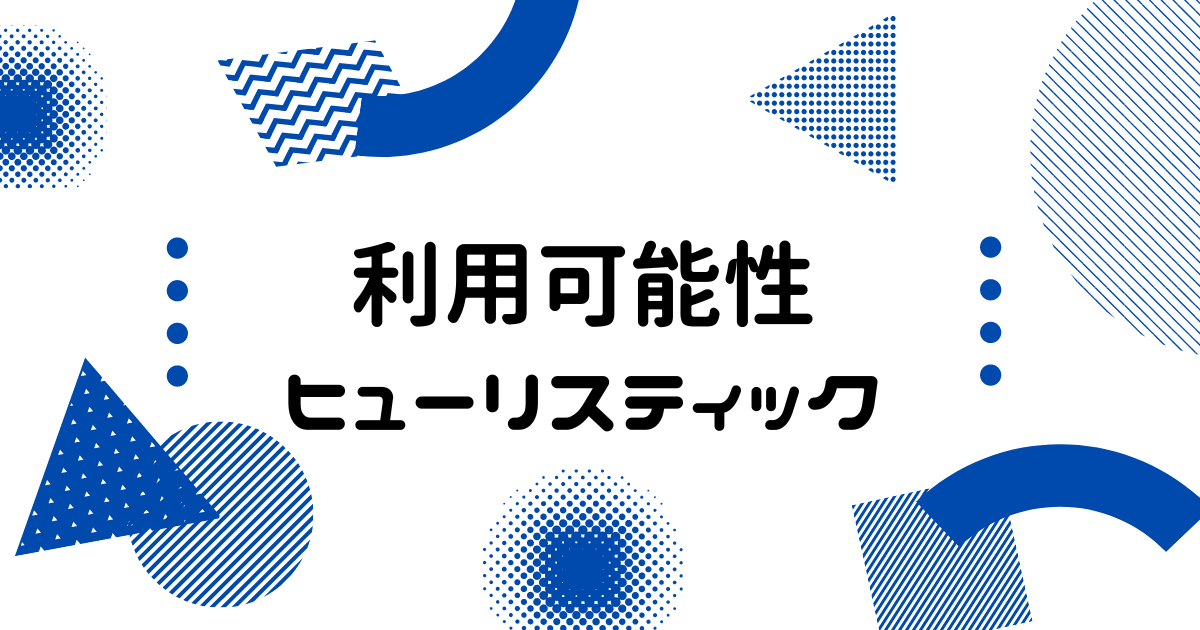
-1.jpg)

利用可能性ヒューリスティックとは|意味・具体例・活用法を解説