ゴルディロックス効果(松竹梅の法則)とは、無難なものを選択しようとするという心理傾向のことです。
たとえば、あなたは「カメラ」を購入しようとしています。さて、あなたは下記の3つのうち、そのカメラを購入するでしょうか。
おそらく「3万円のカメラ」を購入しようと思ったのでは。もちろん、大前提として、それぞれの性能の違いなども検討しなければならないですが。しかし、あなたの経験を振り返ってみても、ほとんどの場合、無難な選択肢に吸い寄せられてきたのではないでしょうか。
しかし、なぜこのような現象が起きてしまうのでしょうか。本記事では、ゴルディロックス効果の心理学的メカニズム、またそれを営業やマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
ゴルディロックス効果とは
無難なものを選択しようとするという心理傾向
ゴルディロックス効果(Goldilocks effect)は、経済や心理学、物理学など様々な分野で用いられる概念で、ある状態がちょうど良い範囲(適度な範囲)にあるという状況を指します。この言葉は、英語の童話「ゴルディロックスと三匹のくまたち」から来ており、物語の中でゴルディロックスが三匹のくまたちの家で、ちょうど良い大きさのベッドやちょうど良い温度のポリッジを見つけるシーンに由来します。
ゴルディロックス効果は、ある状況が過剰でなく不足でもなく、ちょうど良いバランスにあるということを意味します。例えば、経済学では、物価が適度に上昇し、インフレとデフレのバランスが保たれる状態をゴルディロックス経済と言ったりします。また、ゴルディロックス効果は、販売戦略などにも用いられており、松竹梅戦略がそれに当たります。
ゴルディロックス効果の具体例
では、いくつか具体例をみていきましょう。
- スマートフォンの選択
- レストランの選択
- 教育プログラム
事例1:スマートフォンの選択
スマートフォン市場では、低価格帯(松)、中価格帯(竹)、高価格帯(梅)の製品が存在します。消費者は、高性能で高価な高価格帯のスマートフォン(梅)と、低性能で安価な低価格帯のスマートフォン(松)の間で、適切な価格と性能のバランスを持つ中価格帯のスマートフォン(竹)を選ぶ傾向があります。これは、ゴルディロックス効果が働いていると考えられます。
事例2:レストランの選択
レストランを選ぶ際も、ゴルディロックス効果が働くことがあります。例えば、高級な料理を提供する高価なレストラン(梅)、手頃な価格で良質な料理を提供するカジュアルなレストラン(竹)、安価で質が劣るファストフード店(松)がある場合、多くの人は適切な価格と品質のバランスを持つカジュアルなレストラン(竹)を選ぶことが一般的です。
事例3:教育プログラム
教育プログラムやコースを選ぶ際にも、ゴルディロックス効果が働くことがあります。例えば、高度な専門知識を必要とする高難易度のコース(梅)、適度な難易度で一般的な知識を身につけることができる中難易度のコース(竹)、簡単で基本的な知識しか得られない低難易度のコース(松)がある場合、多くの人は適切な難易度と学習効果のバランスを持つ中難易度のコース(竹)を選ぶ傾向があります。
ゴルディロックス効果の実験
では、1980年代の古典的な実験を紹介します。
まず、被験者に、一眼レフカメラとカセットレコーダーのカタログをみてもらいます。カタログには、説明書きや写真と一緒に価格が掲載されています。その際、被験者に下記の指示をしました。
「その中からもしも買うとしたら、これが欲しいと思うモデルをカメラとレコーダーから一つずつ選んでください」
実験の結果、選択肢が2つしかない場合、「高いモデル」と「安いモデル」を選ぶ比率が半分半分となりました。しかし、この選択肢に「さらに高額のモデル」を加えると(つまり、選択肢が3つになると)、なんと被験者の2/3が中間価格となったモデルを選び、「一番高いモデル」と「一番やすいモデル」が半々となったのです。
ゴルディロックス効果はなぜ発動するのか
では、ここからは、ゴルディロックス効果が発動する心理学的理由を紹介します。
- アンカリング効果
- 損失回避
- 代表性ヒューリスティック
心理学1:アンカリング効果
アンカリング効果とは、意思決定などを行う際に、最初に提示された情報に過度に依存するという心理傾向のことです。
たとえば、「6万円で提供します」と言われるよりも、「8万円(アンカー)のところを6万円で提供します」と言われた方が安いと感じてしまいます。つまり、選択肢を3つ用意することで、一番高額の商品がアンカー(基準)とすれば「安い!」と判断され、一番安い商品がアンカー(基準)となれば「品質が高い!」と思われるようになるのです。
心理学2:損失回避バイアス
損失回避バイアスとは、損をすることを嫌うという心理傾向のことです。たとえば、選択肢が2つしかなかった場合を考えてみてください。
この場合、それぞれにデメリットがあることが分かるでしょうか。
つまり、どちらを選択しても損をしてしまうと感じるわけです。しかし、3つの選択肢を用意すれば、真ん中の商品は大きなデメリットの無い商品と判定されるため、損失回避バイアスが働きにくくなります。
心理学3:代表性ヒューリスティック
代表性ヒューリスティックとは、過去の経験から、連想ゲームのように処理される心理傾向のことです。たとえば、メガネをかけている人を見て、「頭が良いに違いない!」と感じた経験はないでしょうか。これはまさに代表性ヒューリスティックの例になります。
もちろん、ゴルディロックス効果と代表性ヒューリスティックには、大きな関係があります。それは、直感で「真ん中=無難」と判断するところです。つまり、3つの商品が並んでいたら、直感で「真ん中を選択するべきだ!」と感じてしまうわけです。
ゴルディロックス効果を営業・マーケティングに活用する方法
ここでは、ゴルディロックス効果を営業・マーケティングに活用する方法を紹介していきます。
- 決定回避の法則
- 価格の順番
- 価格の位置
方法1:決定回避の法則
決定回避の法則とは、選択肢が多すぎると、選択すること自体を回避してしまうという心理傾向のことです。たとえば、顧客に10種類のプランを一気に見せた場合、その中から選択すること自体を面倒だと感じてしまい、不買につながることがあります。
なので、もしも、あなたの扱う商品のプランが多い場合、それを3つにカテゴライズして、提案するようにしましょう。たとえば、下記のような感じになります。
仮に、顧客がカテゴリ2を選択したのであれば、その中からまたD,E,Fという3択から選ばせるのです。すると、選択回避が発動しなくなり、失注を避けることができるようになります。
方法2:価格の順番
価格を提示する際には、一番高額のものから提示するようにしましょう。なぜなら、前述した「アンカリング効果」の影響を使うことができるからです。たとえば、6万円、4万、3万という3つのプランがあるなら、6万のプランから提案するようにしましょう。すると、それがアンカーとなり、4万円のプランを安いと感じさせることができるよになります。
方法3:「横」よりも「縦」に配置
価格を見せる際は、横に配置するのではなく、縦に配置するようにしましょう。なぜなら、人は「上」にあるものを「高額なモノ」、「下」にあるものを「低額なモノ」と一瞬で判断する性質があるからです。
横の配置
6万円→4万円→3万円
縦の配置
まとめ
ゴルディロックス効果とは|相手を誘導する選択の心理学
もし、あなたが事業者であり、扱う商品サービスを自身でコントロールできるのであれば、今すぐゴルディロックス効果に従ったプランを作成するようにしましょう。
一方、あなたが会社の商品を扱う営業マンであるなら、上記で紹介したカテゴライズのテクニックを使ってうまくゴルディロックス効果を活用するようにしてみてください。
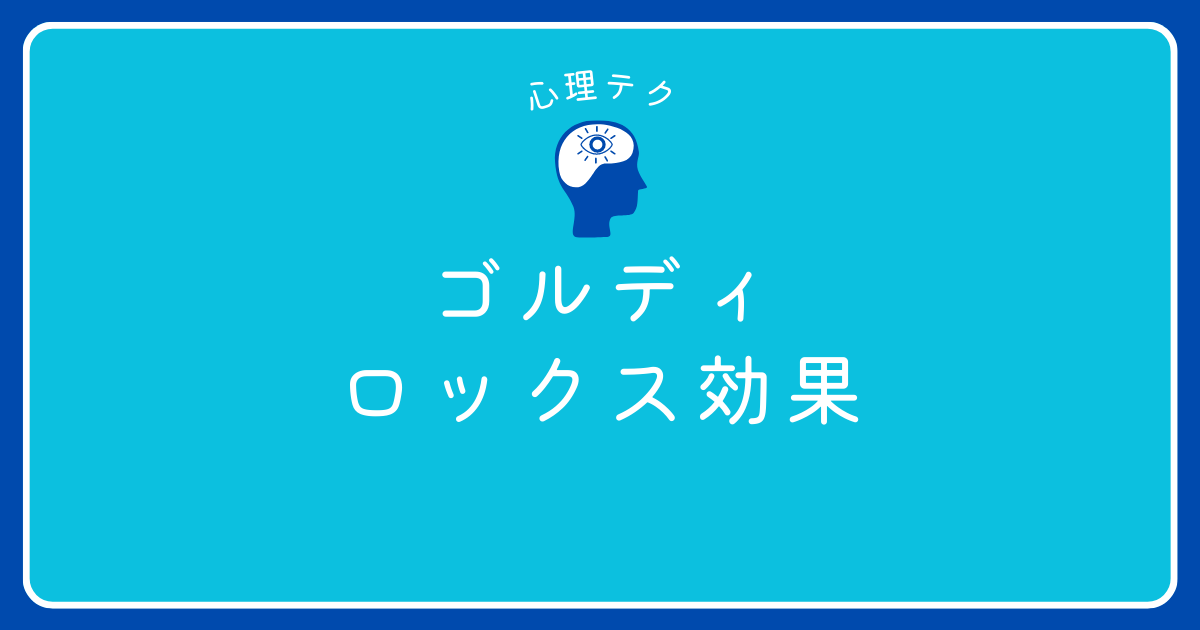
-1.jpg)

ゴルディロックス効果とは|相手を誘導する選択の心理学