代表性ヒューリスティックとは、過去の経験から、連想ゲームのように処理される心理現象のことです。
たとえば、本を読んでいる人を見て「あの人は頭が良いに違いない!」と思ったり、低身長の人がスポーツをしていると聞くと「体操選手なのかな?」と想像したりします。このように、我々は過去の経験から、連想ゲームのように想像することが多々あります。
しかし、なぜこのような現象が起きるのでしょうか。本記事では、代表性ヒューリスティックが発動する心理的メカニズム、またそれを営業やマーケティングに活用する方法などを紹介していきます。
というわけで本日は、
というテーマでブログを執筆していこうと思います。
目次
代表性ヒューリスティックとは
過去の経験から、連想ゲームのように処理される心理現象
代表性ヒューリスティックは、あるものが特定のグループやカテゴリに属する確率を、そのものがグループやカテゴリの典型的な特徴をどれだけ持っているかに基づいて判断します。つまり、「見た目」や「感じ」がそのグループやカテゴリに似ているほど、そのものがそのグループに属すると判断します。
例えば、ある人が白衣を着ていて、メガネをかけているとします。多くの人は、その人が医者である可能性が高いと判断するでしょう。これは、その人が医者の典型的な特徴(白衣やメガネ)を持っているためです。しかし、この方法では、他の重要な情報(例えば、その場所が病院ではないこと)を無視することがあります。
代表性ヒューリスティックは、迅速な判断を行う上で役立つことがありますが、認知バイアスや誤った判断につながることもあります。そのため、このヒューリスティックの限界を理解し、他の情報や方法を活用することが、より適切な判断や意思決定につながります。
代表性ヒューリスティックの具体例
では、いくつか具体例をみていきましょう。
- 職業の判断
- スポーツ選手の評価
- 映画のジャンル予想
事例1:職業の判断
あなたがパーティーで新しい人と出会い、その人が話が上手で社交的だと気づいたとしましょう。その人が営業職や広報職に就いていると判断するのは、代表性ヒューリスティックの働きです。話が上手で社交的な特徴が、営業職や広報職の代表的な特徴として認識されているためです。
事例2:スポーツ選手の評価
バスケットボール選手が非常に背が高い場合、その選手がセンターポジションでプレイしていると判断することは、代表性ヒューリスティックの例です。背が高いことはセンターポジションの選手の代表的な特徴とされているため、その選手がセンターである確率が高いと判断されます。
事例3:映画のジャンル予想
映画の予告編を見て、その映画がアクション映画であると判断することも、代表性ヒューリスティックの例です。予告編に爆発やカーチェイスのシーンがたくさんある場合、それらのシーンはアクション映画の典型的な特徴として認識されているため、その映画がアクション映画であると判断されます。
代表性ヒューリスティックの実験
代表性ヒューリスティックに関する有名な実験の一つは、アモス・ツヴェルスキーとダニエル・カーネマンによって行われた「リンダの問題」です。この実験では、参加者たちにリンダという女性の説明が与えられました。リンダは、以下のようなプロフィールを持っています。
リンダは31歳の独身女性で、大学では哲学を専攻しました。学生時代は社会正義に関心を持ち、反核デモにも参加していました。
その後、参加者たちに以下の2つの記述のうち、リンダにとってより確率が高いと思われるものを選ばせました。
多くの参加者がオプションBを選びました。これは、リンダのプロフィールがフェミニスト活動に関心がある女性の典型的な特徴を持っているためです。しかし、オプションBはオプションAよりも確率が低いはずです。なぜなら、オプションBはオプションAにさらなる条件(フェミニスト活動に参加している)が追加されているため、条件が厳しくなっています。
この実験は、参加者が代表性ヒューリスティックによって誘導され、リンダのプロフィールとフェミニスト活動が関連していると感じたことで、基本的な確率原理に反する判断を行ったことを示しています。つまり、代表性ヒューリスティックが認知バイアスや誤った判断につながることを示す典型的な例です。
代表性ヒューリスティックが発動する理由
代表性ヒューリスティックが発動する心理学的理由は、人間が情報を処理する際に簡略化や省略を行い、直感的に判断を下すことにあります。初心者にも分かりやすく説明するために、以下のポイントを押さえて説明します。
- 情報過多
- カテゴリ化の傾向
- 直感的な判断
理由1:情報過多
私たちは日常生活で大量の情報にさらされています。すべての情報を詳細に分析して判断を下すことは現実的ではないため、人間は情報の一部を取り出して、それを基に判断を行います。代表性ヒューリスティックは、そのような簡略化された情報処理の一つの方法です。
理由2:カテゴリ化の傾向
人間は情報を整理し、理解しやすくするために、自然に物事をカテゴリ化する傾向があります。代表性ヒューリスティックでは、類似性や特徴に基づいて物事をカテゴリに分類し、それに基づいて判断を下すことが一般的です。
理由3:直感的な判断
人間は状況や情報をすばやく判断するために、無意識的に直感を利用します。代表性ヒューリスティックは、直感的な判断を行う際に、類似性や特徴に基づいて物事を評価し、その結果をもとに判断を下すプロセスです。
代表性ヒューリスティックを営業に活用する方法
では、ここからは、代表性ヒューリスティックを営業に活用する方法を紹介していきます。
- 見た目を意識する
- 言葉を意識する
- 話し方を意識する
方法1:見た目を意識する
営業において見た目は、命よりも大切なことだと捉えておいてください。なぜなら、見た目によって、ポジティブかネガティブのどちらのカテゴリに振り分けられるかが大きく左右されるからです。
たとえば、みすぼらしい格好で営業活動をしてしまうと、それだけで「この人は出来ない営業マンだ」とあなたの能力に関係なく判断されてしまいます。このように、見た目はあなたの営業生命を大きく左右することにつながります。なので、営業をする際は、下記のことに気を配るようにしてみてください。
方法2:言葉を意識する
営業において言葉遣いもまた命よりも大切になります。上記と理由は全く一緒です。具体例をみた方が分かりやすいでしょう。
たとえば、「マジで〜」「くそですよね〜」「キモイっすよね〜」という言葉を使う営業マンに対してどのような印象を抱くでしょうか。きっと、悪いイメージを抱くでしょう。なぜなら、ネガティブな言葉を使うと、直感で「この人は不誠実に違いない!」と感じてしまうからです。営業で大きな成果を得たいのであれば、言葉遣いは必ず正すようにしましょう。
方法3:話し方を意識する
営業において、説得力はものすごく大切な要素になります。なぜなら、「この人だったら安心できる!」と思わせることが出来なければ、商品は売れないからです。
では、説得力を高めるためには何をすればいいのでしょうか。結論、「なぜなら〜」という接続詞を使いましょう。これを理由付けと言います。というのも、人は「なぜなら〜」という接続詞を聞くだけで、相手に説得力を感じるということが科学的に分かっているからです。ある研究では、主張だけではなく、理由も添えることで、説得力が1.6倍に跳ね上がったという結果が出ているほどです。
代表性ヒューリスティックをマーケティングに活用する方法
- 高単価戦略
- 松竹梅戦略
- 類似顧客の成功事例
方法1:高単価戦略
我々は「高単価なモノほど質が良い」と勘違いしてしまうという性質があります。つまり、あえて高単価にすることで、質の高いモノというふうにカテゴライズしてしまうのです。これをヴェブレン効果といいます。
ビジネス駆け出しの人たちは、「自信がない…」という理由から低価格で販売してしまいがちですが、高単価にすることで逆に売上が上がる可能性もあります。もしも今必要以上に低価格で販売されている方は、相場よりも少し高い金額に設定してみるのもありますね。
方法2:松竹梅戦略
我々は3つのうち真ん中のものを選びやすいという性質があります。これをゴルディロックス効果といいます。なぜなら、「真ん中=無難」という代表性ヒューリスティックが働くからです。もっと、厳密に言うと、上位商品と下位商品には、それぞれデメリットがあるからです。
なので、結果、中間の商品が選ばれやすくなるのです。なので、サービスを展開するときは、必ず3つのプランを用意するのがおすすめになります。たとえば、何かしらのコンサルタントをしているのであれば、下記のようなプランを提供するのがベストです。
方法3:類似顧客の成功事例
営業活動では、類似の顧客が製品やサービスを利用して成功を収めた事例や評判を紹介することで、顧客に製品やサービスがそのカテゴリに属するものと感じさせることができます。
例えば、あなたがオンライン英会話サービスの営業マンで、同じ目標を持つ顧客がサービスを利用して英語力を向上させた事例を紹介することで、顧客はそのサービスが効果的な英会話学習カテゴリに属すると感じるでしょう。
まとめ
代表性ヒューリスティックとは|意味・具体例・活用法を解説
代表性ヒューリスティックは、少し難しい概念でしたね。しかし、これは我々の日常のあらゆる場面で発動しており、もちろん、営業やマーケティングにも応用されています。
もし、あなたが何かしらの商品を販売する、またはプロモーションをする人間であるなら、本記事を何度も繰り返し読み、代表性ヒューリスティックへの理解を深めていくようにしましょう。
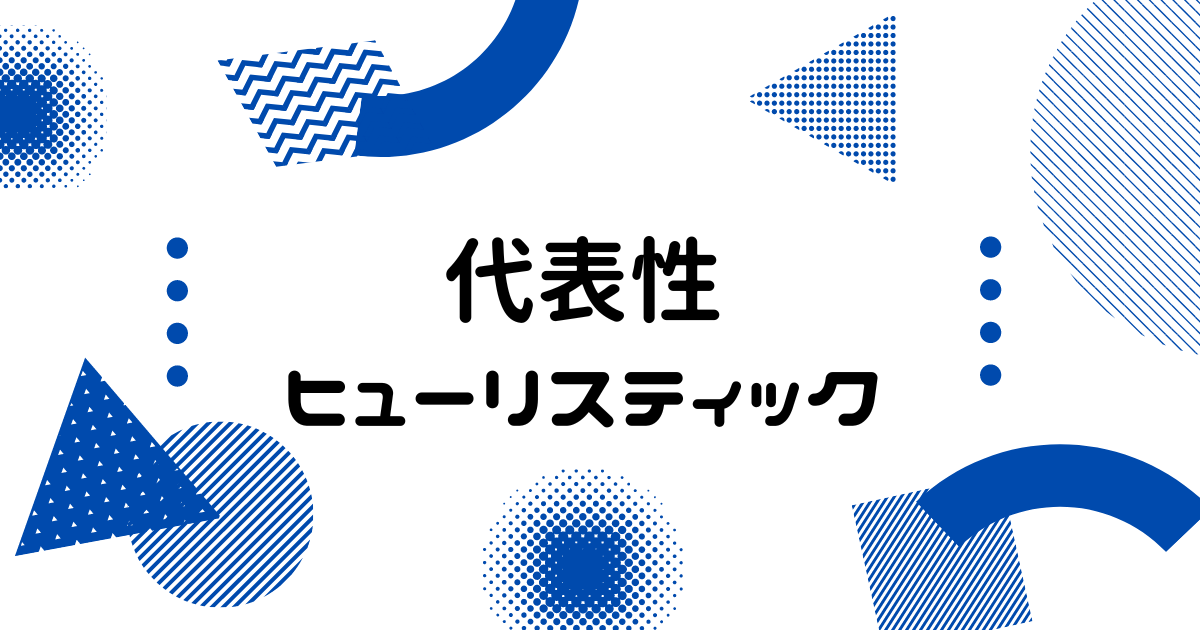
-1.jpg)

代表性ヒューリスティックとは|意味・具体例・活用法を解説