双曲割引|目の前の誘惑に負けてしまう理由とは【営業に活用する方法も紹介】
双曲割引とは、「目の前の価値」を優先して、「遠い未来の価値」を割り引くという心理傾向のことです。 たとえば、「今から1万円をもらう」のと、「1年後に1.2万円をもらう」のとでは、あなたはどちらを選択するでしょうか。びっく...
 行動経済学
行動経済学双曲割引とは、「目の前の価値」を優先して、「遠い未来の価値」を割り引くという心理傾向のことです。 たとえば、「今から1万円をもらう」のと、「1年後に1.2万円をもらう」のとでは、あなたはどちらを選択するでしょうか。びっく...
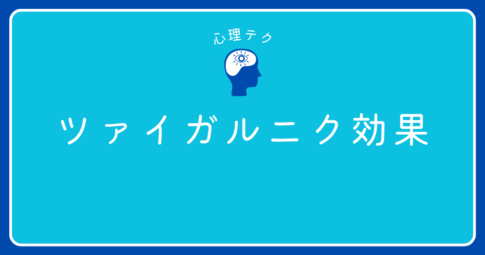 心理テク
心理テクツァイガルニク効果とは、未完了のものが想起そうきされやすくなるという心理現象のことです。 たとえば、アニメを観ている途中で「続きはCMのあと!」なんて言われると、続きが気になって仕方がなくなりますよね。このように、我々に...
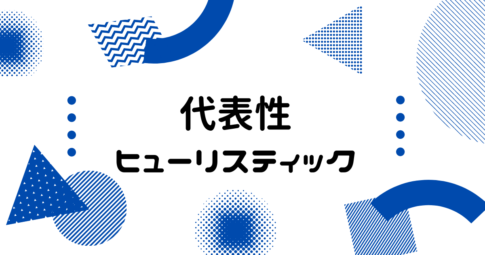 ヒューリスティック
ヒューリスティック代表性ヒューリスティックとは、過去の経験から、連想ゲームのように処理される心理現象のことです。 たとえば、本を読んでいる人を見て「あの人は頭が良いに違いない!」と思ったり、低身長の人がスポーツをしていると聞くと「体操選手...
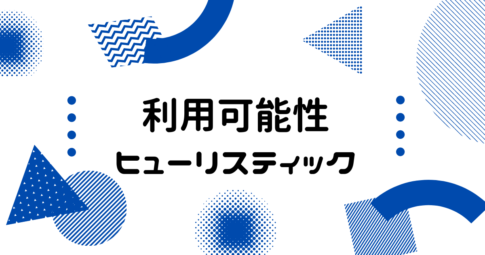 ヒューリスティック
ヒューリスティック利用可能性ヒューリスティックとは、「想起しやすさ」によって、認知が歪められてしまう現象のことです。 いきなり質問ですが、日本で多いのは下記のどちらでしょうか。 きっと多くの人は、自信満々に「コンビニに決まってるじゃん!」...
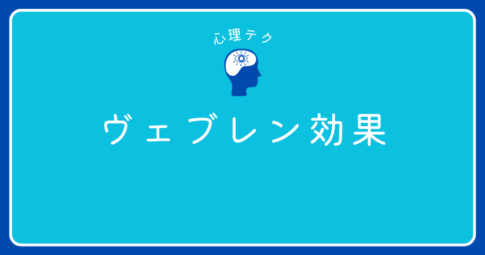 心理テク
心理テクヴェブレン効果とは、価格が上昇するほど、需要が上昇するという心理現象のことです。 たとえば、300万円もする「ロレックス」の時計が欲しいなんて思ったことはありませんか。他にも、「BMW」や「ランボルギーニ」などの高級車を...
 バイアス
バイアスダニング・クルーガー効果とは、能力の低い人は、自分の能力を高く見積もるという心理傾向のことです。 たとえば、学力の無い人に、自分の点数を予想させると、高めに見積もる傾向があり、予想とかけ離れた点数になっていることがありま...
 バイアス
バイアス自己奉仕バイアスとは、成功を自分の資質のためとし、失敗を他者や環境のせいにするという現象のことです。 たとえば、車の衝突事故では、被害者が相手のせいにするのはもちろんですが、加害者側は自己奉仕バイスによって自分の責任を過...
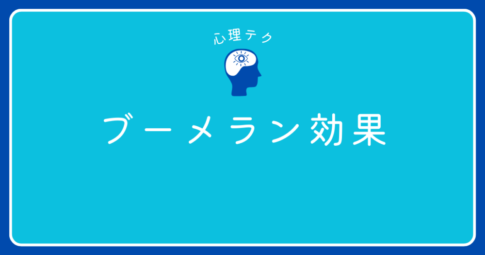 心理テク
心理テクブーメラン効果とは、説得されればされるほど、逆の態度・行動をとってしまうという心理効果です。 たとえば、親に「勉強しなさい!」と言われると、勉強する気が失せたりしたことってありませんか。このように、説得は相手を変えるうえ...
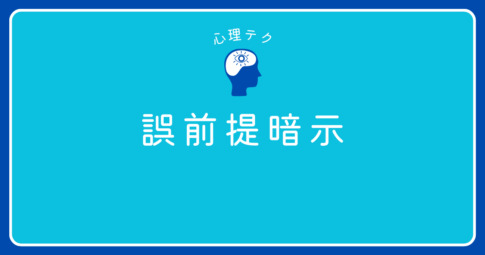 心理テク
心理テク誤前提暗示(ごぜんていあんじ)とは、質問そのものに含まれる前提を受け入れるように誘導する手法のことです。 たとえば、好きな女性をデートに誘う時、「今度、デートしない?」と誘うよりも「今度、ランチかディナーに行かない?」と...
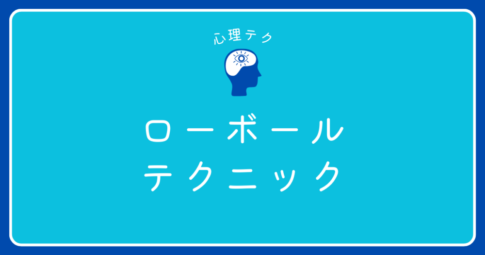 心理テク
心理テクローボールテクニックとは、最初に好条件の要求を承諾させ、後から好条件を引いたり、悪い条件を足したりする心理テクニックのことです。 たとえば、「50%セールス中!」という広告をみて洋服店に入ったものの、その対象は一部の商品...
 バイアス
バイアス確証バイアスとは、自分にとって都合の良い情報ばかりを集め、都合の悪い情報は排除しようとする心理傾向のことです。 たとえば、あなたは血液型がB型の人にどのようなイメージを持っているでしょうか。きっと、「B型の人」=「自己中...
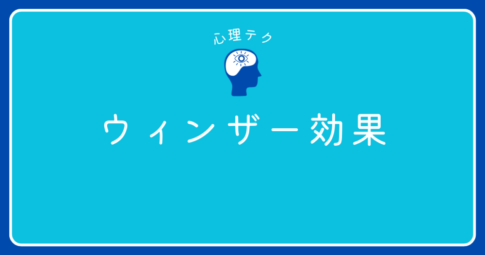 心理テク
心理テクウィンザー効果とは、本人から直接言われるよりも、「第三者」から言われた方が、信ぴょう性や信頼が高まるという心理効果のことです。 たとえば、営業パーソンから直接「この商品は素晴らしいんですよ!」と伝えられるよりも、友達から...
 バイアス
バイアスバイアスとは、「思考のクセ」のことです。 たとえば、メガネをかけている人に対して、「頭が良さそう〜」と評価してしまうことってありませんか。実は、これはハローバイアスというバイアスによるものです。つまり、「メガネをかけてい...
 バイアス
バイアス損失回避バイアスとは、損失を回避したいという傾向ことです。 たとえば、パチンコで1万円負けてしまい、その損失をカバーするためにさらにお金を投下してしまうのは、「損をしたくない!」という欲求が働くからです。このように、我々...
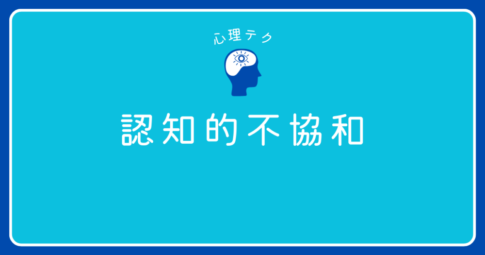 心理テク
心理テク認知的不協和とは、人が自分の信念、態度、価値観、または行動の間に矛盾や不整合を感じることによって生じる心理的な不快感のことです。 たとえば、「夜更かし」がまさにその典型的な例ですね。 「早く寝たい」という態度と「夜更かし...
 バイアス
バイアス現状維持バイアス とは、現状維持をしようとする人間の本能のことです。 たとえば、下記のようなことを考えたことはないでしょうか。 上記のように、我々はこの現状維持バイアスに苦しめられ、あなたの目標達成することを妨げてきます...
 バイアス
バイアス保有効果とは、所有しているモノに対して、不当に価値付けしてしまう心理傾向のことです。 たとえば、リサイクルショップなどで、買取をお願いした際に、思っていた以上に安く値付けされたと感じたことはありませんか。もちろん、買取側...
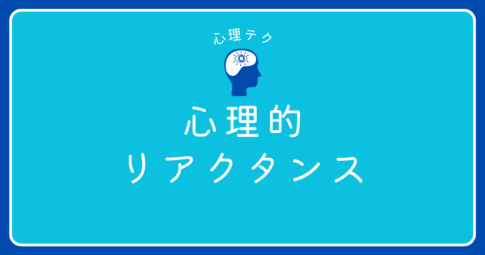 心理テク
心理テク心理的リアクタンスとは、自由を制限されるほど、その自由を取り戻そうとする心理現象のことです。 たとえば、「絶対に見るなよ!」と言われたら、それが気になってしかたがなくなりますよね。他にも、「親から勉強しなさい!」と言われ...
 バイアス
バイアスピーク・エンドの法則とは、あらゆる経験の快楽・苦痛は、「絶頂時」と「終了時」の快楽・苦痛の度合いで決まるという法則です。 たとえば、テーマパークでは、ひとつのアトラクションを楽しむために、長時間並ぶという苦痛に耐えなけれ...
 バイアス
バイアスサンクコスト効果とは、特定の対象にコスト(時間・お金・労力など)をかけると、それを不当に価値付けしてしまうという心理傾向のことです。 たとえば、パチンコで1万円負けてしまったとする。しかし、多くの人たちはその損を取り返そ...
 心理テク
心理テク営業成果が思うように伸びないと悩んでいるあなた、こんな新たなアプローチ方法はいかがですか? それは、「ランチョンテクニック」です。 この戦術は、食事を共有することで顧客との信頼関係を築き、取引成功へと導くものです。 この...